2024年12月の市議会レポート
12月の議会は、翌3月に審議される次年度予算に向けて、予算に取り入れて欲しいことを取り上げるのに適している時期になります。
他の議員の一般質問や市民の方からの陳情書にもそのような傾向が見られました。
今年は特に、私を含めて値上げを予定している海老名市の給食費に関する話題が多かったように感じました。
他の議員の一般質問や市民の方からの陳情書にもそのような傾向が見られました。
今年は特に、私を含めて値上げを予定している海老名市の給食費に関する話題が多かったように感じました。
一般質問では、以下の3点について行いました。
・小中学校の給食について
・小中学校の給食について
・子育て中のリフレッシュについて
・平和事業について
1つ目は、牛乳の選択制について、会食時間の長さ(短さ)について、給食費の保護者負担を増やさない対応について取り上げました。
2つ目は、子育て中のリフレッシュのために利用できる、一時保育とファミリーサポートセンターに関して、枠の少なさや予約の取りづらさの改善について取り上げました。
3つ目は、終戦80年、海老名市が平和都市宣言をしてから40年を迎える、2025年の平和事業の計画について、「ピースメッセンジャー」や「平和ワークショップ」など、市民参加型のイベントを提案し、実現の可能性について伺いました。
1つ目は、牛乳の選択制について、会食時間の長さ(短さ)について、給食費の保護者負担を増やさない対応について取り上げました。
2つ目は、子育て中のリフレッシュのために利用できる、一時保育とファミリーサポートセンターに関して、枠の少なさや予約の取りづらさの改善について取り上げました。
3つ目は、終戦80年、海老名市が平和都市宣言をしてから40年を迎える、2025年の平和事業の計画について、「ピースメッセンジャー」や「平和ワークショップ」など、市民参加型のイベントを提案し、実現の可能性について伺いました。
また、今回は給食費の据え置きを求める陳情書が2件提出され、いずれも趣旨了承されました。
意見書はありいあいこから「核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を求める意見書」が提出され、【賛成10/反対9/離席2】の僅差で可決されました。
また、今回は給食費の据え置きを求める陳情書が2件提出され、いずれも趣旨了承されました。
意見書はありいあいこから「核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を求める意見書」が提出され、【賛成10/反対9/離席2】の僅差で可決されました。
それでは、それぞれの議題について、詳しく振り返りたいと思います。
海老名市議会の議案や賛否の結果などは、ホームページで公開されています。
傍聴や中継に関する案内も載っていますので、こちらもぜひご覧ください。
海老名市議会ホームページ https://ebina.gijiroku.com/index.asp
海老名市議会の議案や賛否の結果などは、ホームページで公開されています。
傍聴や中継に関する案内も載っていますので、こちらもぜひご覧ください。
海老名市議会ホームページ https://ebina.gijiroku.com/index.asp
-----------------------------------------------------------------------------
Index
○文教社会常任委員会
○一般質問
・小中学校の給食について
・子育て中のリフレッシュについて
・平和事業について
・平和事業について
○意見書
・「核兵器禁止条約締約国会議」へのオブザーバー参加を求める意見書 意見書案第10号
-----------------------------------------------------------------------------
○文教社会常任委員会
・陳情書:海老名市学校給食費の公費負担の継続を求める陳情
・陳情書:給食費の保護者負担が増えることのないよう、公費の補助を増やし、子どもたちの食を守ることを求める陳情書
海老名市内で活動する2つの市民団体から学校給食の公費負担を継続(増額)し、保護者負担が増えないことを求める陳情書が提出され、趣旨了承されました。
食材費高騰への対策として給食費値上げは避けられませんが、子育て世帯の家計を圧迫することの影響は大きいため、公費での補助は必須です。
陳情書の中には「質・量ともに落とさず子どもたちのために財源を作り出し保護者負担増額のないようにお願いします」との切実な願いも。
給食無償化はしないと断言している市長ですが、せめて値上げはしない判断をしてほしいと市民も議会も求めています。
市の答弁からは前向きに検討する意向が感じられましたがどうなるか、来年度予算に注目しましょう!
・陳情書:重度身体障害者や家族に寄り添った対応を求める陳情書
本陳情は9月議会に提出されて趣旨不了承となったものが再度内容を改めて提出されたものです。前回のタイトルも重度障がい者や家族に寄り添った対応を求めるものでしたが、その想いに応えられていないことは大変心苦しいことだと思います。
この陳情で求めている具体的な4点(※)については、先進的な一部の自治体で行われていることであったり、全国的な課題であったりと、ただちに海老名市で対応することは難しいことかもしれません。しかし、障害福祉をさらに向上させていくためには、このような当事者家族の声に耳を傾けながらひとつひとつ前に進めていく姿勢を持つことが重要だと思います。なぜなら、私も含めて障がい者の方の実情を知らない人は多くおり、まだまだ障がい者の権利が十分に守られているとは言えない現状があるからです。結果として趣旨不了承となりましたが、この陳情を海老名市の障がい福祉の向上に向けての貴重な意見として活かすことが望ましいと考えます。
※以下の4点です。
1.障がい福祉課の現場のケースワーカーが足りない状況が切実であり、増員をお願いしたい
2.365日対応できる相談事務所またはそれと同様のセクションを考えていただきたい
3.訪問介護事業所の他に地域参加型の併設サポート事業のような枠を広げた制度を一緒に考えて欲しい
4.緊急時、たとえば当事者の体調が悪化した場合、家族の病気や怪我以外でも人手の必要なときは支援を考えて欲しい
・陳情書:給食費の保護者負担が増えることのないよう、公費の補助を増やし、子どもたちの食を守ることを求める陳情書
海老名市内で活動する2つの市民団体から学校給食の公費負担を継続(増額)し、保護者負担が増えないことを求める陳情書が提出され、趣旨了承されました。
食材費高騰への対策として給食費値上げは避けられませんが、子育て世帯の家計を圧迫することの影響は大きいため、公費での補助は必須です。
陳情書の中には「質・量ともに落とさず子どもたちのために財源を作り出し保護者負担増額のないようにお願いします」との切実な願いも。
給食無償化はしないと断言している市長ですが、せめて値上げはしない判断をしてほしいと市民も議会も求めています。
市の答弁からは前向きに検討する意向が感じられましたがどうなるか、来年度予算に注目しましょう!
・陳情書:重度身体障害者や家族に寄り添った対応を求める陳情書
本陳情は9月議会に提出されて趣旨不了承となったものが再度内容を改めて提出されたものです。前回のタイトルも重度障がい者や家族に寄り添った対応を求めるものでしたが、その想いに応えられていないことは大変心苦しいことだと思います。
この陳情で求めている具体的な4点(※)については、先進的な一部の自治体で行われていることであったり、全国的な課題であったりと、ただちに海老名市で対応することは難しいことかもしれません。しかし、障害福祉をさらに向上させていくためには、このような当事者家族の声に耳を傾けながらひとつひとつ前に進めていく姿勢を持つことが重要だと思います。なぜなら、私も含めて障がい者の方の実情を知らない人は多くおり、まだまだ障がい者の権利が十分に守られているとは言えない現状があるからです。結果として趣旨不了承となりましたが、この陳情を海老名市の障がい福祉の向上に向けての貴重な意見として活かすことが望ましいと考えます。
※以下の4点です。
1.障がい福祉課の現場のケースワーカーが足りない状況が切実であり、増員をお願いしたい
2.365日対応できる相談事務所またはそれと同様のセクションを考えていただきたい
3.訪問介護事業所の他に地域参加型の併設サポート事業のような枠を広げた制度を一緒に考えて欲しい
4.緊急時、たとえば当事者の体調が悪化した場合、家族の病気や怪我以外でも人手の必要なときは支援を考えて欲しい
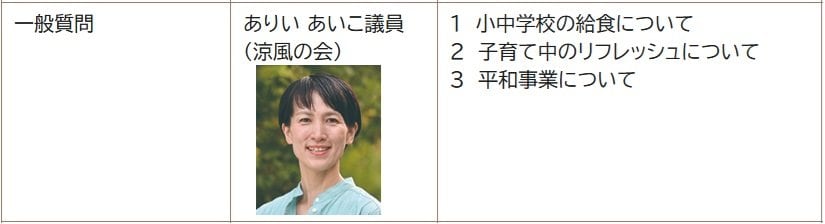
画像引用:海老名市議会ホームページより
https://ebina.gijiroku.com/g07_Video_Search.asp?kaigi=98&Sflg=1
https://ebina.gijiroku.com/g07_Video_Search.asp?kaigi=98&Sflg=1
○一般質問
一般質問では、以下の3点について行いました。
○1点目 給食で提供される牛乳について
給食時間が短いのではないかという声を聞いています。学年が低い場合や食べるのに時間がかかる子にとっては、最後まで食べきれない、おかわりができないという状況があると聞いています。
給食時間が十分にないと、必要な栄養が取れない、満腹にならない、早く食べなければというストレスを感じる、残食が多くなるなど、様々な問題が考えられるとともに、給食時間が楽しく豊かな時間ではなく、むしろ苦痛に感じてしまう子が一定数いることも 懸念されます。
そこで 海老名市の小中学校の給食にかけている時間と残食の量について伺いました。
○3点目 給食費の負担について
物価高騰の影響を受けて、海老名市では来年度から給食費の保護者負担を上げることが条例では決まっております。
しかしながら子育て世帯の家計状況が厳しいことに変わりはなく、上述の通り、給食費の据え置きを求める陳情書も2件上がってきました。
また東京都23区は給食を無償化にしていたり、近隣では今年度は厚木市が無償化をスタートしております。日本政府においても2023年12月に発表した、こどもみらい戦略の中で学校給食無償化に向けての全国調査を実施するとしており、今年6月には結果報告もされるなど、動き出しています。
つまり、今まで保護者負担が当たり前だった 給食費について、これからは公費で負担するべきだと、社会が大きく変わる過渡期であるということだと思います。
国が無償化を実現するまでに、自治体間で給食費の保護者負担に大きな格差が生まれてしまうことについて、一部無償化の議論や完全無償化の議論も含めまして、保護者負担を増やさない 対応、このことが必要だと考え、市の見解を伺いました。
1点目について、牛乳の提供を受けない児童生徒の割合について、 現在小学校が約3.6%、中学校が約14%、小中学校合計で約7%とのことでした。
また残量については、残本数で回答があり、令和3年度が2.78%、令和4年度が1.59%、令和5年度が1.27%でした(東柏ケ谷小学校分含まず)。本数、重量にすると、約26,000本、5,200キログラムです。
開封後、廃棄しているものは他のおかずと混ぜているので、集計はできていませんが、食育やフードロスの観点からも、少し飲んで廃棄するというのはあまり良いことではないと感じています。
一方で、給食で提供している栄養バランスの中には、牛乳の分も含まれているということもあります。
他の自治体の先進事例として、東京都多摩市では、給食の牛乳の食品ロスと多様なニーズへの対応として、2023年から牛乳の選択性の取り組みを始めています。説明用の資料として、学校給食における牛乳の必要性、カルシウムなどについて図解も用いてしっかりと記載をした上で、それでも停止したい場合は理由を問わず、申請すれば可能であるということを分かりやすく明記しています。
このように、説明をしっかりした上で、飲まないという選択もできることをわかりやすく伝える取り組みを取り入れて頂きたいと思います。
また牛乳の提供を受けない場合は、申請すれば給食費からも差し引かれますので、しっかり周知して頂いて、改善していって頂きたいと思います。
2点目の給食時間については、小学校は40分または45分、中学校は30分また35分となっており、そのうち前後の配膳、後片付けを除くと更に短くなります。残食の量については、今年度1学期の数値で1人1食あたり、小学校が79g(水分を切った後の重量)、中学校が 118g(水分を含んだ重量)でした。
給食の食べ残しというのは、SDGs、フードロスの観点から、教育委員会としても課題と捉えており、ポスター配布、保護者への食育のお便りの配信、動画の配信など、啓発に努めているとのことでした。
残食の量は、食べる時間の長さや提供される量に関係があると思われるので、アンケートの実施や、給食時間を試験的に伸ばしてみるなどの調査を行って、検証していって頂きたいことを伝えました。
3点目の給食費の保護者負担については、他の議員からも質問があり、その中で市長からも、社会情勢と合わせて給食費の条例の改正はしていくけれども、実際の保護者負担については、きちんと市民の声を聞いて対応していくというような答弁がありました。
私からも、保護者負担を増やさないような対応をして頂きたいことを改めて要望しました。
・小中学校の給食について
・子育て中のリフレッシュについて
・平和事業について
それぞれの質問と答弁の概要を以下に記載します。
1 小中学校の給食について
○1点目 給食で提供される牛乳について
給食の牛乳を巡っては全国的に様々な議論があり、私の周りにも色々な考えの保護者の方がいらっしゃいます。
給食での牛乳の提供に疑問を持っていない方は良いのですが、アレルギーや乳糖不耐症など体質的な問題がある方、和食と合わないと考える方、牛乳をあえて 日常的に飲ませないようにしている方などもいらっしゃいます。
海老名市においては、小学校入学時に提出する書類の中で食事のみ提供を受けるにチェックをすれば、特に医師の診断がなくても牛乳の提供を受けなくて良いという柔軟な対応をしていますが、あまり周知されておりません。
我慢して飲んでいる子や、少しだけ飲んで後を廃棄するという子も多くいることを懸念していますが、牛乳の提供を受けないよう 申請している児童生徒の割合と、給食における牛乳の残量について伺いました。
給食での牛乳の提供に疑問を持っていない方は良いのですが、アレルギーや乳糖不耐症など体質的な問題がある方、和食と合わないと考える方、牛乳をあえて 日常的に飲ませないようにしている方などもいらっしゃいます。
海老名市においては、小学校入学時に提出する書類の中で食事のみ提供を受けるにチェックをすれば、特に医師の診断がなくても牛乳の提供を受けなくて良いという柔軟な対応をしていますが、あまり周知されておりません。
我慢して飲んでいる子や、少しだけ飲んで後を廃棄するという子も多くいることを懸念していますが、牛乳の提供を受けないよう 申請している児童生徒の割合と、給食における牛乳の残量について伺いました。
○2点目 会食時間の長さについて
給食時間が短いのではないかという声を聞いています。学年が低い場合や食べるのに時間がかかる子にとっては、最後まで食べきれない、おかわりができないという状況があると聞いています。
給食時間が十分にないと、必要な栄養が取れない、満腹にならない、早く食べなければというストレスを感じる、残食が多くなるなど、様々な問題が考えられるとともに、給食時間が楽しく豊かな時間ではなく、むしろ苦痛に感じてしまう子が一定数いることも 懸念されます。
そこで 海老名市の小中学校の給食にかけている時間と残食の量について伺いました。
○3点目 給食費の負担について
物価高騰の影響を受けて、海老名市では来年度から給食費の保護者負担を上げることが条例では決まっております。
しかしながら子育て世帯の家計状況が厳しいことに変わりはなく、上述の通り、給食費の据え置きを求める陳情書も2件上がってきました。
また東京都23区は給食を無償化にしていたり、近隣では今年度は厚木市が無償化をスタートしております。日本政府においても2023年12月に発表した、こどもみらい戦略の中で学校給食無償化に向けての全国調査を実施するとしており、今年6月には結果報告もされるなど、動き出しています。
つまり、今まで保護者負担が当たり前だった 給食費について、これからは公費で負担するべきだと、社会が大きく変わる過渡期であるということだと思います。
国が無償化を実現するまでに、自治体間で給食費の保護者負担に大きな格差が生まれてしまうことについて、一部無償化の議論や完全無償化の議論も含めまして、保護者負担を増やさない 対応、このことが必要だと考え、市の見解を伺いました。
1点目について、牛乳の提供を受けない児童生徒の割合について、 現在小学校が約3.6%、中学校が約14%、小中学校合計で約7%とのことでした。
また残量については、残本数で回答があり、令和3年度が2.78%、令和4年度が1.59%、令和5年度が1.27%でした(東柏ケ谷小学校分含まず)。本数、重量にすると、約26,000本、5,200キログラムです。
開封後、廃棄しているものは他のおかずと混ぜているので、集計はできていませんが、食育やフードロスの観点からも、少し飲んで廃棄するというのはあまり良いことではないと感じています。
一方で、給食で提供している栄養バランスの中には、牛乳の分も含まれているということもあります。
他の自治体の先進事例として、東京都多摩市では、給食の牛乳の食品ロスと多様なニーズへの対応として、2023年から牛乳の選択性の取り組みを始めています。説明用の資料として、学校給食における牛乳の必要性、カルシウムなどについて図解も用いてしっかりと記載をした上で、それでも停止したい場合は理由を問わず、申請すれば可能であるということを分かりやすく明記しています。
このように、説明をしっかりした上で、飲まないという選択もできることをわかりやすく伝える取り組みを取り入れて頂きたいと思います。
また牛乳の提供を受けない場合は、申請すれば給食費からも差し引かれますので、しっかり周知して頂いて、改善していって頂きたいと思います。
2点目の給食時間については、小学校は40分または45分、中学校は30分また35分となっており、そのうち前後の配膳、後片付けを除くと更に短くなります。残食の量については、今年度1学期の数値で1人1食あたり、小学校が79g(水分を切った後の重量)、中学校が 118g(水分を含んだ重量)でした。
給食の食べ残しというのは、SDGs、フードロスの観点から、教育委員会としても課題と捉えており、ポスター配布、保護者への食育のお便りの配信、動画の配信など、啓発に努めているとのことでした。
残食の量は、食べる時間の長さや提供される量に関係があると思われるので、アンケートの実施や、給食時間を試験的に伸ばしてみるなどの調査を行って、検証していって頂きたいことを伝えました。
3点目の給食費の保護者負担については、他の議員からも質問があり、その中で市長からも、社会情勢と合わせて給食費の条例の改正はしていくけれども、実際の保護者負担については、きちんと市民の声を聞いて対応していくというような答弁がありました。
私からも、保護者負担を増やさないような対応をして頂きたいことを改めて要望しました。
2 子育て中のリフレッシュについて
○1点目 一時保育について
保育園が実施している 一時保育を利用してリフレッシュしたいという方から、予約したくても空きがない、空いている園を探して、各園に連絡するのが大変など、利用がしづらいという声を聞いています。そこで、 現在海老名市内で一時保育を実施している園数と定員数について伺いました。
保育園が実施している 一時保育を利用してリフレッシュしたいという方から、予約したくても空きがない、空いている園を探して、各園に連絡するのが大変など、利用がしづらいという声を聞いています。そこで、 現在海老名市内で一時保育を実施している園数と定員数について伺いました。
また、元々は一時保育を実施していたけれど、一般の保育枠を増やすために一時保育 をやめている保育園が何園あるか、公立の保育園が一時保育を実施していない理由についても伺いました。
○2点目 ファミリーサポートセンターについて
一時保育以外の選択肢として、ファミリーサポートセンターを利用することもできますが、利用したい人に対して援助会員が少なく、マッチングが難しいということを聞いています。実際にまだ小さな子供を育てながら援助会員をしている方も多く、1人で何件か受け持つこともあるなど、少ない人数の中で何とか回っているという印象です。
そこで、ファミリーサポートセンターの利用人数と援助会員の状況について、またファミリーサポートセンターの意義と課題について伺いました。
そこで、ファミリーサポートセンターの利用人数と援助会員の状況について、またファミリーサポートセンターの意義と課題について伺いました。
1点目については、今年度は市内認可保育園16園で実施しており、いずれの園も通常の保育と合わせて実施しているとの回答でした。
また一時預かりの受け入れの可否、人数などについては、園の体制などにより、流動的であることから、各園の運営に委ねているため、予約が取りにくい状況になっていますが、これは市の方でも認識しているとのことでした。
なお公立保育園については、一般の保育定員数を最大限に確保していることから、一時預かり事業の実施は難しい状況とのことでした。しかし、来年度開所する新園では一時預かりを実施予定であり、今後についても、新園の整備の際には、本事業の実施を積極的に働きかけていきたいと、前向きな答弁を頂きました。
また一時預かりの受け入れの可否、人数などについては、園の体制などにより、流動的であることから、各園の運営に委ねているため、予約が取りにくい状況になっていますが、これは市の方でも認識しているとのことでした。
なお公立保育園については、一般の保育定員数を最大限に確保していることから、一時預かり事業の実施は難しい状況とのことでした。しかし、来年度開所する新園では一時預かりを実施予定であり、今後についても、新園の整備の際には、本事業の実施を積極的に働きかけていきたいと、前向きな答弁を頂きました。
2点目について、ファミリーサポートセンターの令和5年度末における利用会員の登録数は、1,266名、援助を行う援助会員の登録数は172名でした。
利用会員のうち、約9割の方がもしもの時に備えての登録となっており、実際に援助を利用された方は1,260名中、143名でした。
援助会員の方々もご自身が子育て中であったり、仕事の合間を塗っての援助であったりということで、実際援助を行っていただいた方は 172 名中 70名でした。
市としては、最優先課題は保育園を増やして待機児童をなくすことであり、それに伴い一時保育の枠も増えていく、との見解でした。また、ファミリーサポートセンターについても援助会員不足が課題であり、リフレッシュとしての利用は少ないのが現状です。
そうすると、海老名市で子育てをしている方で、子どもを預けてリフレッシュの時間を取ることのハードルが高い状況というのは今後も続いてしまう可能性があります。すでにリフレッシュ時間を持つことを仕方ないと諦めてしまっている方が一定数いることを是非真摯に受け止めてほしいと訴えました。
そのための具体的な対応策として、市として一時預かり専門の場所を作るという考えがないかも聞きました。例えば子どもセンターの中で一時預かりを実施してほしいという要望は市民からも上がっているそうです。しかし今は預かりスペースや人員体制がないため現状での実施は難しいとのことでしたが、子育て中のリフレッシュはとても大切なので今後も研究をしていくとの回答でした。
利用会員のうち、約9割の方がもしもの時に備えての登録となっており、実際に援助を利用された方は1,260名中、143名でした。
援助会員の方々もご自身が子育て中であったり、仕事の合間を塗っての援助であったりということで、実際援助を行っていただいた方は 172 名中 70名でした。
市としては、最優先課題は保育園を増やして待機児童をなくすことであり、それに伴い一時保育の枠も増えていく、との見解でした。また、ファミリーサポートセンターについても援助会員不足が課題であり、リフレッシュとしての利用は少ないのが現状です。
そうすると、海老名市で子育てをしている方で、子どもを預けてリフレッシュの時間を取ることのハードルが高い状況というのは今後も続いてしまう可能性があります。すでにリフレッシュ時間を持つことを仕方ないと諦めてしまっている方が一定数いることを是非真摯に受け止めてほしいと訴えました。
そのための具体的な対応策として、市として一時預かり専門の場所を作るという考えがないかも聞きました。例えば子どもセンターの中で一時預かりを実施してほしいという要望は市民からも上がっているそうです。しかし今は預かりスペースや人員体制がないため現状での実施は難しいとのことでしたが、子育て中のリフレッシュはとても大切なので今後も研究をしていくとの回答でした。
市長は、「子育て政策にゆとりがあればいいが今は保育園待機児童ゼロを目指すことで手一杯であり、ゆとりができた段階でできていくだろう」との見解でしたが、このままではワンオペ育児をしている家庭は疲弊してしまいます。もっと危機感をもって同時進行で取り組んでもらいたいことを求めました。
3 平和事業について
3 平和事業について
2025年で終戦から80年となりますが、私たちの生活の中で戦争について語る機会はほとんどなくなり、日本の戦争の被害や加害について学ぶ機会はどんどん減っている現状があります。戦争体験を語り継ぐ活動をしている市民団体も、高齢者など特定の人しかイベントに集まらないことに課題を感じており、どうやって 若い世代に戦争のことを伝えていくかは、これからの社会が取り組むべき大きな課題であると考えます。
さらに今の日本は平和憲法に守られ戦争しない国とは簡単には言えない状況です。 2015年の安保法制、2022年の安保3 文書の決定などにより、アメリカと軍事 一体化していく道を突き進んでいます。そのため 軍事費も43兆円にまで引き上げるとしており、今年の10月には自衛隊とアメリカ軍が今までで最大規模の軍事演習を行うなど、沖縄本島や離島では日米両政府の指導のもと、急速な軍事要塞化も進行しています。
さらに今の日本は平和憲法に守られ戦争しない国とは簡単には言えない状況です。 2015年の安保法制、2022年の安保3 文書の決定などにより、アメリカと軍事 一体化していく道を突き進んでいます。そのため 軍事費も43兆円にまで引き上げるとしており、今年の10月には自衛隊とアメリカ軍が今までで最大規模の軍事演習を行うなど、沖縄本島や離島では日米両政府の指導のもと、急速な軍事要塞化も進行しています。
このような状況の中、戦争や平和に対する考え方も非常に多様化しており、今一度戦争について、平和について、世代を超えて考えることはとても重要であり、市として取り組む平和事業においても、時代の変化に合わせて進化していくことが必要ではないかと考えます。2025年は終戦から80年目であると同時に、海老名市が平和都市宣言をしてから40年の節目でもあります。海老名市平和事業推進に関する条例にもあるように、市民と共同して平和事業を推進するという姿勢に立ち返り、多くの市民の積極的な参加を促すような平和事業の展開を創意工夫で行うことが望ましいと考えます。
そこで、特に若い世代へのアプローチを強めて欲しいとの想いから、「ピースメッセンジャー」と「平和ワークショップ」について提案・要望をしました。
ピースメッセンジャーは、 広島や長崎に子供たちを派遣して、現地で学習したことを市内で発表してもらうという取り組みで、平和派遣などと呼ばれています。
近隣の自治体では、平塚市、茅ヶ崎市、秦野市が行っていることを確認しているものの、海老名市では実施の検討をしたことがないようです。
しかしながら、自治体によって様々な取り組みが行われているので、先進事例の状況を確認するなど、情報収集に努めたいとのことでした。
平和ワークショップは、子供や若者が主体的に平和について関わる取り組みとして、西東京市では2023年から「子供若者平和 ワークショップ」を実施しています。聞き取りをしたところ、ワークショップに参加したことをきっかけに、普段の生活の中での選択や他のイベントへの参加など、個人の行動変容につながっているということでした。
市としては、現在のところ実施の予定はないものの、平和事業の実施にあたり、若い方々に興味を持って頂くきっかけとして大変有効な事例と考えており、他の自治体の先進事例を参考にしながら、情報収集を進めていきたいとのことでした。
-----------------------------------------------------------------------------
そこで、特に若い世代へのアプローチを強めて欲しいとの想いから、「ピースメッセンジャー」と「平和ワークショップ」について提案・要望をしました。
ピースメッセンジャーは、 広島や長崎に子供たちを派遣して、現地で学習したことを市内で発表してもらうという取り組みで、平和派遣などと呼ばれています。
近隣の自治体では、平塚市、茅ヶ崎市、秦野市が行っていることを確認しているものの、海老名市では実施の検討をしたことがないようです。
しかしながら、自治体によって様々な取り組みが行われているので、先進事例の状況を確認するなど、情報収集に努めたいとのことでした。
平和ワークショップは、子供や若者が主体的に平和について関わる取り組みとして、西東京市では2023年から「子供若者平和 ワークショップ」を実施しています。聞き取りをしたところ、ワークショップに参加したことをきっかけに、普段の生活の中での選択や他のイベントへの参加など、個人の行動変容につながっているということでした。
市としては、現在のところ実施の予定はないものの、平和事業の実施にあたり、若い方々に興味を持って頂くきっかけとして大変有効な事例と考えており、他の自治体の先進事例を参考にしながら、情報収集を進めていきたいとのことでした。
-----------------------------------------------------------------------------
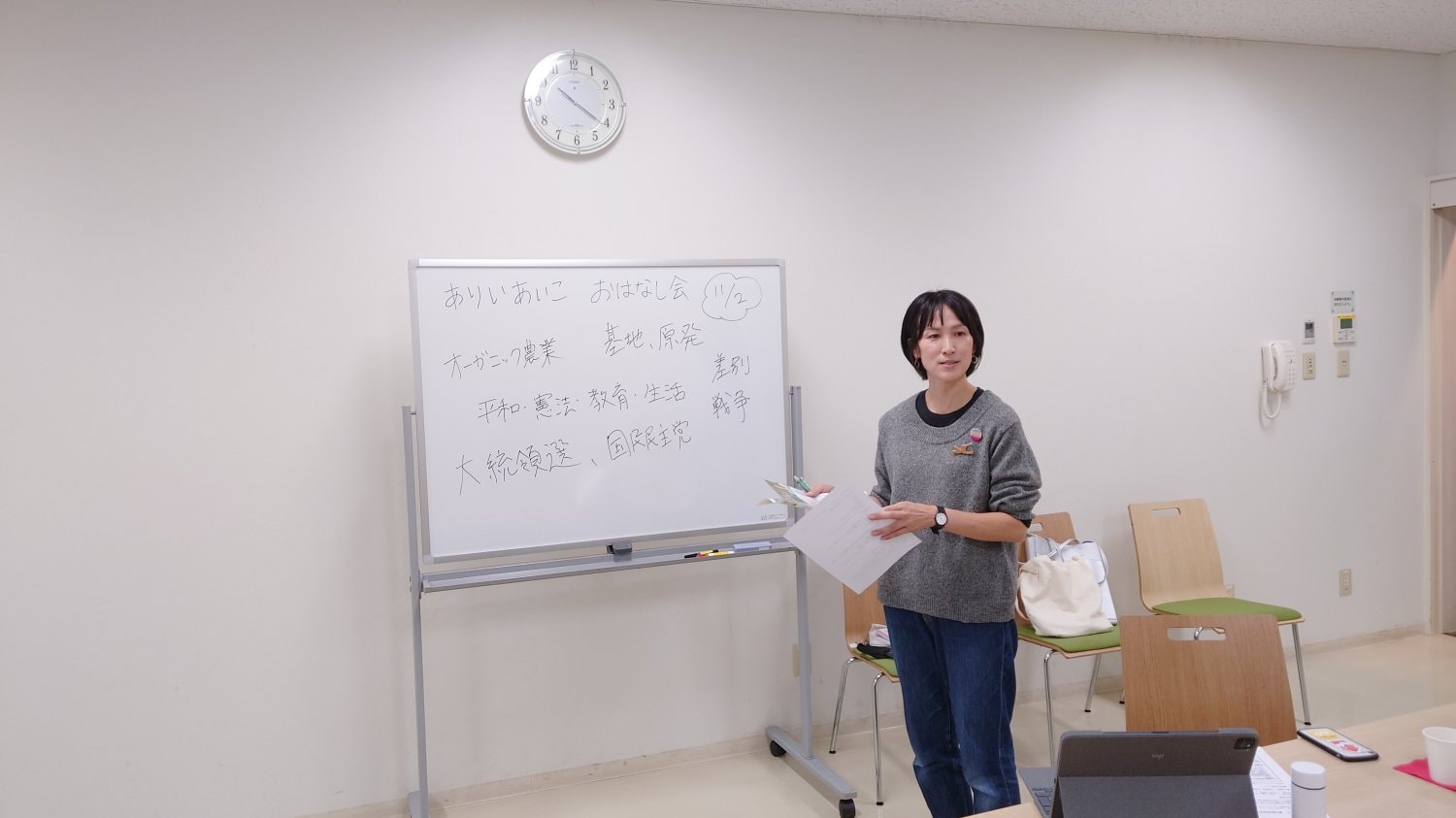
○意見書
・核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を求める意見書 意見書案第5号
核兵器廃絶に向けてできることを
昨年10月に日本被団協がノーベル平和賞を受賞したことを受けて、この機に自分にも何かできないかと思い、海老名市議会から国へ意見書を出せないかと動きました。初めは条約への批准を求める内容で出そうと思いましたが、各議員への打診の結果、会議へのオブザーバー参加を求める内容に変更しました。
全員賛成を目指し文案調整をしましたが、政進会と参政党の議員は賛成できないとの回答。公明党は初めは難しそうでしたが、国政でオブザーバー参加を求める動きもあり賛成できるとの回答を得られました。海老名維新の会は賛成したい意向がややありつつも、党の方針もあり明確な回答は得られませんでした。その他の方はみなさん賛成の意を示してくれました。
予告なしでの質問と、反対討論あり
採決当日、提案者として提案説明をしましたが、説明後に提案者への質問に手が挙がりました。質問があると思っていなかったので完全に油断していました!
そこからはぶっつけ本番でのやりとり。質問の趣旨は、日米安保を基盤とした体制や不拡散条約(NPT)がある中で、核兵器禁止条約に参加することは矛盾しないか、日米関係を揺るがさないか、混乱を招かないか、といったものでした。これに対しては私は、日本は日米安保がありながらも唯一の被爆国という特殊な立ち位置にあること、たとえアメリカの核の傘の下にあっても、同時に核廃絶を訴えることは可能であり必要だと答えました。
そもそも今の日米安保を基盤とする安全保障の在り方に疑問を持ち圧倒的に平和外交が足りないと思っている人も沢山います。被爆国として核廃絶は譲れないとう強い気概を持って外交をしてほしい、日本が核禁条約に前向きな一歩を踏み出すことで国内で安全保障や核廃絶に向けた議論が活発になってほしいと回答しました。
さらに別の方から反対討論もありました。理由は核廃絶への想いは分かるが、現在核保有国の脅威がある中ではただの理想に過ぎない、といった趣旨でした。
安全保障を巡る3つの立場が浮き彫りに
今回のやりとりを通じて大きく3つの考え方があることが分かりました。
①日米同盟を堅持することで平和を維持することが重要だという考え方
②アメリカ支配からの独立のために日本も軍や核を持つ必要があるという考え方
③軍拡はアメリカの戦争に巻き込まれるリスクを高めるだけで日本を守れない。徹底した平和外交で他国と信頼関係を築くことが重要という考え方
核兵器廃絶に向けてできることを
昨年10月に日本被団協がノーベル平和賞を受賞したことを受けて、この機に自分にも何かできないかと思い、海老名市議会から国へ意見書を出せないかと動きました。初めは条約への批准を求める内容で出そうと思いましたが、各議員への打診の結果、会議へのオブザーバー参加を求める内容に変更しました。
全員賛成を目指し文案調整をしましたが、政進会と参政党の議員は賛成できないとの回答。公明党は初めは難しそうでしたが、国政でオブザーバー参加を求める動きもあり賛成できるとの回答を得られました。海老名維新の会は賛成したい意向がややありつつも、党の方針もあり明確な回答は得られませんでした。その他の方はみなさん賛成の意を示してくれました。
予告なしでの質問と、反対討論あり
採決当日、提案者として提案説明をしましたが、説明後に提案者への質問に手が挙がりました。質問があると思っていなかったので完全に油断していました!
そこからはぶっつけ本番でのやりとり。質問の趣旨は、日米安保を基盤とした体制や不拡散条約(NPT)がある中で、核兵器禁止条約に参加することは矛盾しないか、日米関係を揺るがさないか、混乱を招かないか、といったものでした。これに対しては私は、日本は日米安保がありながらも唯一の被爆国という特殊な立ち位置にあること、たとえアメリカの核の傘の下にあっても、同時に核廃絶を訴えることは可能であり必要だと答えました。
そもそも今の日米安保を基盤とする安全保障の在り方に疑問を持ち圧倒的に平和外交が足りないと思っている人も沢山います。被爆国として核廃絶は譲れないとう強い気概を持って外交をしてほしい、日本が核禁条約に前向きな一歩を踏み出すことで国内で安全保障や核廃絶に向けた議論が活発になってほしいと回答しました。
さらに別の方から反対討論もありました。理由は核廃絶への想いは分かるが、現在核保有国の脅威がある中ではただの理想に過ぎない、といった趣旨でした。
安全保障を巡る3つの立場が浮き彫りに
今回のやりとりを通じて大きく3つの考え方があることが分かりました。
①日米同盟を堅持することで平和を維持することが重要だという考え方
②アメリカ支配からの独立のために日本も軍や核を持つ必要があるという考え方
③軍拡はアメリカの戦争に巻き込まれるリスクを高めるだけで日本を守れない。徹底した平和外交で他国と信頼関係を築くことが重要という考え方
私は③の考え方を支持していますが、みなさんはいかがでしょうか?すぐに答えのでない難しい問題です。これから平和についてじっくりゆっくり話せる場を作っていきたいと思います。
拮抗しましたが、結果としては賛成多数で採択されました!これは本当に嬉しいことで、意見書は海老名市議会から日本政府へ届けられます。せめてオブザーバー参加を!この声が大きくなり、日本政府を動かす原動力となりますように!
意見書については、市のホームページで見ることができますので、リンクを張っておきます。ぜひご覧いただけると幸いです。
https://ebina.gijiroku.com/g07_iken.asp
拮抗しましたが、結果としては賛成多数で採択されました!これは本当に嬉しいことで、意見書は海老名市議会から日本政府へ届けられます。せめてオブザーバー参加を!この声が大きくなり、日本政府を動かす原動力となりますように!
意見書については、市のホームページで見ることができますので、リンクを張っておきます。ぜひご覧いただけると幸いです。
https://ebina.gijiroku.com/g07_iken.asp
