
自然とともに歩むお米作り
徳島県美馬市は、徳島の西部に位置し、『にし阿波』と呼ばれる地域の一つです。
吉野川沿いに広がる田園風景は、人々の心を癒してくれます。
しかし、他の地域と同様に高齢化が進み、耕作放棄地が増え続けています。
そんな中、2016年にことりねのお米作りがスタートしました。
3畝ほどの小さな田んぼを借り、友人農家から分けてもらった苗を植えたのが始まりです。
初めは慣れないことばかりで、稲刈りに想定外の時間がかかり、天日干しは農道のガードレールを使う…そんな試行錯誤の日々でした。
今では田んぼも広がり、約2町(6000坪)の規模になりました。
ことりねのお米作りは、昔ながらの手作業を大切にしています。
・ 苗を1本ずつ手植え
・収穫は手刈り
・竹で組み立てたハザ掛けで天日干し
・足踏み脱穀機で脱穀
さらに、農薬や肥料を使わず、田んぼから生まれた藁や籾殻を田んぼに返しています。
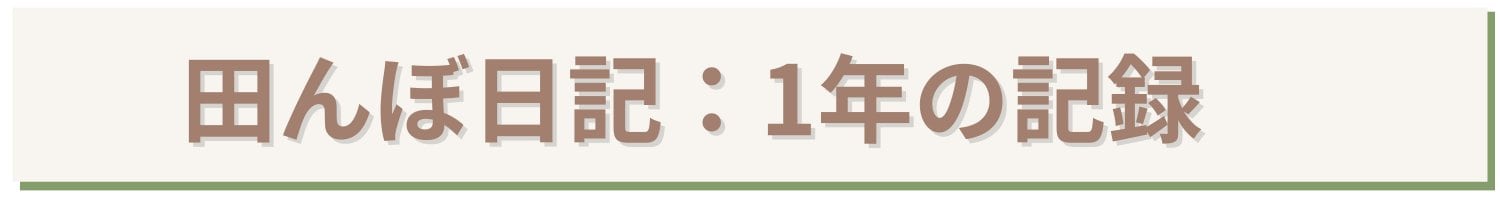
kotorineのお米作りの年間種ジュール
3~5月 浸水・苗床の準備・播種・育苗
5月下旬〜6月いっぱい 田植え
7~9月 草取り・水の管理
10~11月 稲刈り
順に足踏み脱穀・籾摺り
11月中旬 いただきます
3~5月 浸水・苗床の準備・播種・育苗
5月下旬〜6月いっぱい 田植え
7~9月 草取り・水の管理
10~11月 稲刈り
順に足踏み脱穀・籾摺り
11月中旬 いただきます


種籾に命を吹き込む第一歩
3月上旬から中旬にかけて、大切に保管していた種籾を選別し、浸水させて芽出しを行います。
まず、「塩水選」という工程で塩水に種籾を浸し、浮いてきた軽い種籾を取り除きます。
こうして選ばれた中身の詰まった種籾だけをネットに入れ、水に浸します。


次は苗を育てる大切な工程、「苗代作り」と「播種」です。
苗を育てるためのスペースは、田んぼの中に直接作ります。
一定の大きさに整えたら、種籾を蒔き、その上に赤土をかぶせ、板などで丁寧に踏み固めていきます。
こうすることで雑草の発生をある程度抑えられますが、自然の力には敵いません。
それでも芽を守る工夫を続けます。
一定の大きさに整えたら、種籾を蒔き、その上に赤土をかぶせ、板などで丁寧に踏み固めていきます。
こうすることで雑草の発生をある程度抑えられますが、自然の力には敵いません。
それでも芽を守る工夫を続けます。
さらに、種籾が鳥たちに食べられてしまわないよう、不織布を上からかけて保護します。
ただし、保温用のビニール(マルチ)は使用せず、自然の温度に任せて苗がゆっくりと成長するのを見守ります。
ただし、保温用のビニール(マルチ)は使用せず、自然の温度に任せて苗がゆっくりと成長するのを見守ります。
約2週間後、芽が出そろう頃にはいよいよ次の成長段階へ進みます。
この「ゆっくり育てる」工程こそが、私たちの自然と共にある農法の大切な要素です。
この「ゆっくり育てる」工程こそが、私たちの自然と共にある農法の大切な要素です。


特製の定規
田植えを成功させるための大切な準備。
特に欠かせないのが、マサツグさん特製の定規です!
特に欠かせないのが、マサツグさん特製の定規です!
kotorineのお米作りでは、株間を40〜45センチ間隔にして、1本ずつ丁寧に植えています。
この間隔は品種によって調整し、稲がしっかり育つための理想的な空間を確保します。
この間隔は品種によって調整し、稲がしっかり育つための理想的な空間を確保します。
この特製定規は、苗を真ん中に置き、角を基準に植えていくシンプルで効果的なツールです。
これを使うことで、見た目も美しく整った田植えが実現します。
これを使うことで、見た目も美しく整った田植えが実現します。
また、田んぼの耕運はトラクターを持つ友人にお願いしていますが、細かな部分はトンボ(手作業用の道具)を使って調整します。
水が均一に行き渡るように整えることで、後の草取り作業がぐっと楽になります。
水が均一に行き渡るように整えることで、後の草取り作業がぐっと楽になります。
準備から手間を惜しまないのが、kotorineのお米作りのこだわりです!


苗とり
田植えは、品種にもよりますが5月下旬から6月にかけて行います。
苗床で育った稲の中から、5〜6葉が出ていて茎が太いものを慎重に選び、ゆっくり引き抜きます。
根張りが強いので、力任せに引っ張らないのがコツです。
苗床で育った稲の中から、5〜6葉が出ていて茎が太いものを慎重に選び、ゆっくり引き抜きます。
根張りが強いので、力任せに引っ張らないのがコツです。
稗(ヒエ)と間違えないよう注意も必要。
稲は葉が分かれる部分に産毛のような毛が生えているので、それを目印にします
。選別しながら進めるため、とても時間がかかる作業です。
稲は葉が分かれる部分に産毛のような毛が生えているので、それを目印にします
。選別しながら進めるため、とても時間がかかる作業です。
実は私は少し苦手ですが、娘はこの作業が好きで黙々とこなしてくれます。
その姿は、まるで稲とおしゃべりしているようで、とても可愛らしい光景です。
その姿は、まるで稲とおしゃべりしているようで、とても可愛らしい光景です。
土と自然を感じる
集めた苗を田んぼに運び、手作りの定規を使って丁寧に植えていきます。
田んぼには柔らかい部分や硬い部分など、それぞれの個性があり、植えながら発見する楽しさがあります。
田んぼには柔らかい部分や硬い部分など、それぞれの個性があり、植えながら発見する楽しさがあります。
お日様で温まった場所やひんやりした奥の方、足元の温度を感じたり、小さな生き物たちに出会ったりしながら田植えを進めます。
我が家では素足で田んぼに入りますが、虫やカエルが苦手な方は「田靴」という専用の長靴が便利です。
ホームセンターで手軽に購入できますよ。
我が家では素足で田んぼに入りますが、虫やカエルが苦手な方は「田靴」という専用の長靴が便利です。
ホームセンターで手軽に購入できますよ。
余裕が出てきたら、田靴を脱いで泥の中に足を入れてみてください。
心地よいアーシングと、自然の泥パック体験が楽しめます!
心地よいアーシングと、自然の泥パック体験が楽しめます!


生命力が広がる瞬間
稲が枝分かれする現象を「分けつ」と呼びます。
種から出た茎の根元から新しい茎が次々と育つ、この生命力あふれる姿は、稲作の醍醐味の一つです。
種から出た茎の根元から新しい茎が次々と育つ、この生命力あふれる姿は、稲作の醍醐味の一つです。
一般的な稲作では、苗1株で茎が20本程度になると分けつが止まります。
しかしkotorineの田んぼでは、幅広く間隔を空けて植えることで、1本の苗から80〜100本近い分けつが起こることもあります。
根がしっかり張り、茎が太くなるこの植え方は、特に在来種「旭一号」と相性抜群です。
しかしkotorineの田んぼでは、幅広く間隔を空けて植えることで、1本の苗から80〜100本近い分けつが起こることもあります。
根がしっかり張り、茎が太くなるこの植え方は、特に在来種「旭一号」と相性抜群です。
この方法は、熊本の農家さんから学びました。
その田んぼの分けつのすごさには、驚きと感動がありました。
自然の力を活かす農法が、稲の可能性を広げてくれます。
その田んぼの分けつのすごさには、驚きと感動がありました。
自然の力を活かす農法が、稲の可能性を広げてくれます。


稲の小さな奇跡
出穂(しゅっすい)は、茎の中から薄緑色の穂が出てきます。
その穂に咲く小さな花々は、一つの穂に約100〜200個もあり、それぞれが2時間ほどだそうです。
虫眼鏡で観察したくなりました。
虫眼鏡で観察したくなりました。
咲いた花はやがて籾(お米)へと成長します。
この時期は台風やゲリラ豪雨といった心配事もありますが、お米は自然のリズムの中で力強く帳尻を合わせて成長します。
この時期は台風やゲリラ豪雨といった心配事もありますが、お米は自然のリズムの中で力強く帳尻を合わせて成長します。
稲が教えてくれるのは、私たちの対策も大切ですが、まずはその生命力を信じて見守ること。
自然の力を感じる貴重な季節です。
自然の力を感じる貴重な季節です。

実りの喜びを迎える時
いよいよ待ちに待った稲刈りです。
一本ずつ丁寧に植えた稲は根張りがしっかりしており、茎も太いため、ギザギザの歯を持つノコギリ鎌がおすすめです。
3〜4束を刈り取り、前年度の藁を一晩湿らせたもので束ねます。
地力の高いところでは分けつの量がすごいので、ひと束刈るのに手で掴めないくらいに大きな株もあります。
一本ずつ丁寧に植えた稲は根張りがしっかりしており、茎も太いため、ギザギザの歯を持つノコギリ鎌がおすすめです。
3〜4束を刈り取り、前年度の藁を一晩湿らせたもので束ねます。
地力の高いところでは分けつの量がすごいので、ひと束刈るのに手で掴めないくらいに大きな株もあります。
この作業は、家族で過ごす大切な時間でもあり、「稲刈りメディテーション」と呼ぶほど没頭して行います。笑
特に旭1号は背が高く脱粒しやすい品種なので、刈り取りからハザがけにかけるまで慎重に丁寧に進めます。
時間のかかる作業ではありますが、収穫の喜びは何物にも代えられません。実りの瞬間を、家族や仲間と一緒に楽しみます。
稲刈りはその年にもよりますが、約1ヶ月続きます。
後半は稲刈りしながら、足踏み脱穀もしていきます。
時間のかかる作業ではありますが、収穫の喜びは何物にも代えられません。実りの瞬間を、家族や仲間と一緒に楽しみます。
稲刈りはその年にもよりますが、約1ヶ月続きます。
後半は稲刈りしながら、足踏み脱穀もしていきます。


天日干しで引き出すおいしさ
刈り取った稲は束ねて竹で組んだ稲架(はさ)にかけ、天日干しでじっくり乾燥させます。
太陽の力を借りてゆっくり乾燥させることで、お米の甘みや旨みがさらに引き立ちます。
太陽の力を借りてゆっくり乾燥させることで、お米の甘みや旨みがさらに引き立ちます。
乾燥ムラを防ぐため、稲架に掛けるときは7:3に分けて交互に配置する工夫をしています。
この手間が、より均一に仕上がる秘訣です。
この手間が、より均一に仕上がる秘訣です。
稲架がずらりと並ぶ風景は圧巻で、見ているだけで豊かさを感じます。
この美しい光景がもっと広がる未来を願いながら、丁寧に作業を進めています。
この美しい光景がもっと広がる未来を願いながら、丁寧に作業を進めています。


手間を楽しむお米づくり
稲架かけで乾燥させた稲は、次に「脱穀」の工程へ進みます。
足踏み脱穀機を田んぼに持ち込み、穂先から籾を丁寧に外します。
この明治時代末期に開発された脱穀機は、電気を使わず足で動かすため、自然とリズムを感じられる作業です。
ギコギコと回転する音や足で踏む感触を楽しみながら進める脱穀は、昔ながらの魅力が詰まっているのでぜひ体験してほしいです。
足踏み脱穀機を田んぼに持ち込み、穂先から籾を丁寧に外します。
この明治時代末期に開発された脱穀機は、電気を使わず足で動かすため、自然とリズムを感じられる作業です。
ギコギコと回転する音や足で踏む感触を楽しみながら進める脱穀は、昔ながらの魅力が詰まっているのでぜひ体験してほしいです。
脱穀後の藁は来年のために一部を保存し、残りは田んぼへ返します。
藁は再び土に還り、次のお米作りの支えになります。
脱穀した籾には稲の葉や藁くずが混ざっているため、これをさまざまな方法で取り除く必要があります。
なかでも風の力を利用する方法が唐箕を使った風選(ふうせん)です。
風が吹くときに、籾と藁くずが混ざったものを高いところから少しずつ落とし、重い籾は下に落とし、軽い藁くずやゴミは遠くに飛ばす方法です。
木製の唐箕を譲ってもらい大切に使っています。
藁は再び土に還り、次のお米作りの支えになります。
脱穀した籾には稲の葉や藁くずが混ざっているため、これをさまざまな方法で取り除く必要があります。
なかでも風の力を利用する方法が唐箕を使った風選(ふうせん)です。
風が吹くときに、籾と藁くずが混ざったものを高いところから少しずつ落とし、重い籾は下に落とし、軽い藁くずやゴミは遠くに飛ばす方法です。
木製の唐箕を譲ってもらい大切に使っています。
さらに、籾摺りや色選を経て、品種によっては手作業で最終選別を行い、丁寧にお客様のもとへお届けします
種籾から米粒一粒まで、すべて手間と愛情をかけて育てるkotorineの米づくり。
五感をフルに使い、大自然の恵みを最大限に受け取って仕上げたお米を、ぜひ味わってみてください。
種籾から米粒一粒まで、すべて手間と愛情をかけて育てるkotorineの米づくり。
五感をフルに使い、大自然の恵みを最大限に受け取って仕上げたお米を、ぜひ味わってみてください。
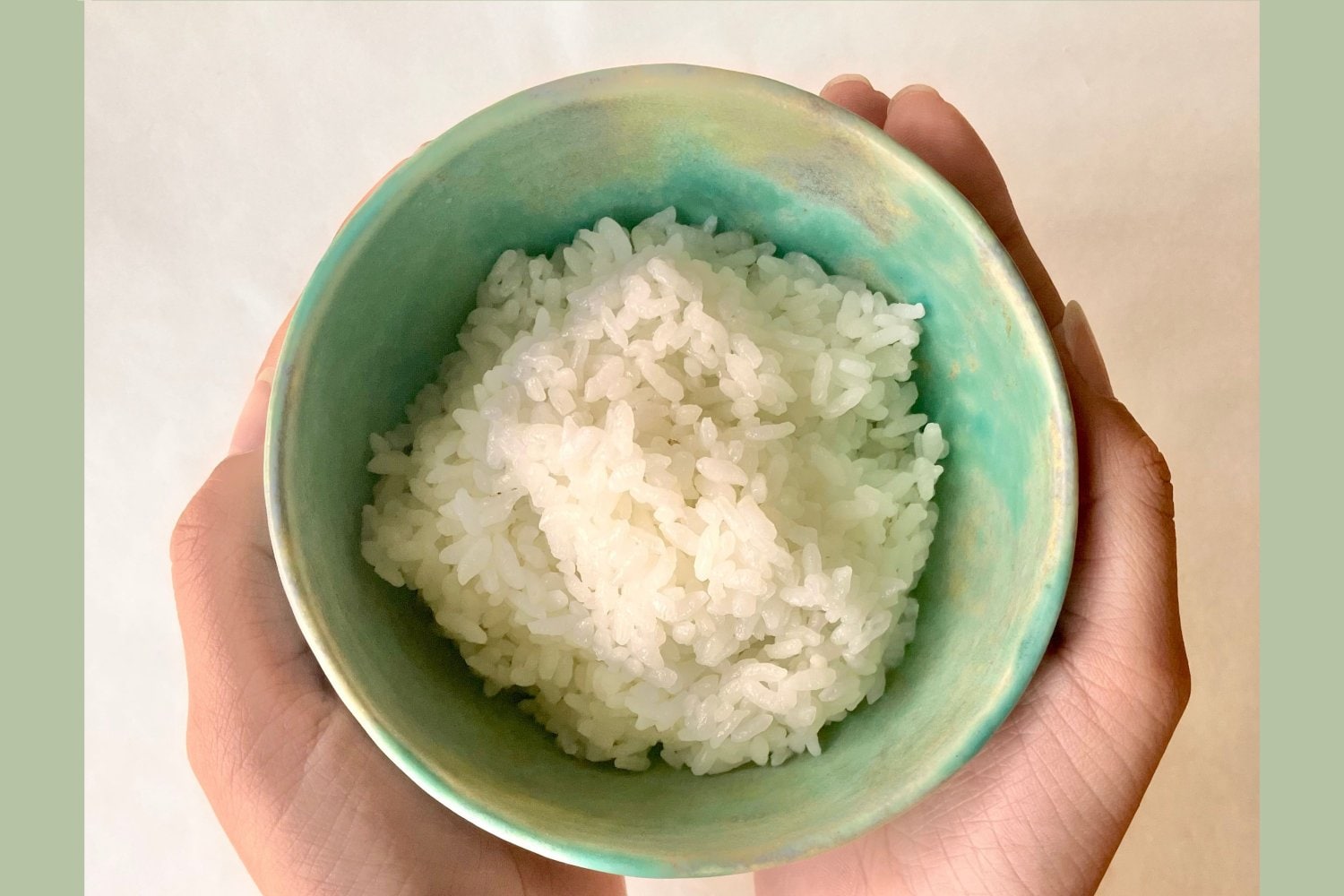


120cm超えの稲と未来への想い
旭1号は背が高く、通常でも120〜130cmほどに成長します。
この写真の田んぼは草取りが追いつかず、草と競り合うように稲がさらに伸び、驚くほどの高さに。
娘(当時150cm)と並ぶ稲の長さから、その成長ぶりがよくわかります。
この写真の田んぼは草取りが追いつかず、草と競り合うように稲がさらに伸び、驚くほどの高さに。
娘(当時150cm)と並ぶ稲の長さから、その成長ぶりがよくわかります。
この田んぼはかつて耕作放棄地でしたが、地力が高く、稲の根張りもとてもしっかりしていました。
しかし後にソーラーパネルを設置するため、田んぼを持ち主に返却しました。
しかし後にソーラーパネルを設置するため、田んぼを持ち主に返却しました。



