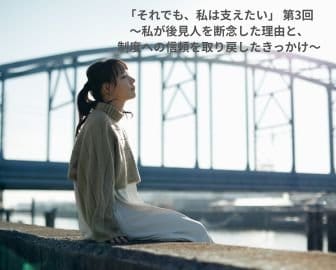2025.07.28
「それでも、私は支えたい」 第3回 〜私が後見人を断念した理由〜
「それでも、私は支えたい」
第3回
~私が後見人を断念した理由と、制度への信頼を取り戻したきっかけ~
前回のブログでは、余命わずかな叔母のために「法定後見申請」に挑戦しようと決意した経緯と、その最初の壁となった“診断書”取得についてお伝えしました。
(👉まだの方はこちらからご覧ください:https://home.tsuku2.jp/storeBlogDetail.php?scd=0000246017&no=17195)
今回はその続き、第3回として、
「なぜ私が後見人になることを断念したのか」
そして、
「それでも制度を信じようと思えた出来事」
についてお話しします。
相続や介護の現場では、「気持ちだけではどうにもならない」現実も多くあります。
それでも、支える側の心が折れてしまわないように──。
私の体験が、誰かのヒントになれば幸いです。
―――――――――――――――――――――
「もし自分が後見人になれたら、伯母のことをしっかり支えたい」
そんな想いで動き出した私でしたが、現実の壁は想像以上に高いものでした。
7〜8年前に目にした、成年後見制度に対する批判的な記事。
「一度裁判所に任せてしまったら、弁護士や司法書士にすべてを委ねるしかなく、本人の希望も通らなくなる」
そうした不安な情報を見て以来、私は“法定後見=避けたいもの”というイメージをずっと持ち続けていました。
けれども、昨年参加した税理士さんのセミナーで、その考えは少しずつ変わっていきました。
認知症になってしまった場合でも、必ずしも他人が後見人になるとは限らない。
家族が後見人になるか、第三者にお願いするか、選べる制度であるということを知ったのです。
しかし現実には、多くの人が裁判所に任せる選択をしているため、第三者が就任するケースが多く、「裁判所が必ず第三者を選ぶ」という誤解が生まれてしまっているのだと、ようやく理解できました。
現実的な「距離」の壁
実際に今回、青森の伯母の後見申請について、司法書士さんから「どちらを希望されますか?」と確認されたとき、私は迷いなく「私がなります」と答えていました。
「家庭裁判所に一度か二度出向く必要があります」と言われても、
「遠くてもやるしかない」と覚悟していました。
ところが、伯母が病院から介護施設に移ったことで、状況が一変します。
施設長さんとお話しするなかで、次のようなことが分かってきました。
• 月に1〜2回は、直接本人の様子を見に行く必要がある
• 定期的に家庭裁判所への報告が必要
• 預金の管理や引き出しも後見人の仕事(伯母の口座は地元の信用金庫のみ)
つまり、「一度だけ行けば終わり」ではなかったのです。
関東に住む私が、定期的に青森に通うことの難しさ、また口座移管の手続きの煩雑さ――。
介護施設の施設長さんは社会福祉士でもあり、
ご自身も法定後見人としての経験がある方でした。
だからこそ「遠方のご親族が担うのは、現実的に難しいですよ」と率直に教えてくださったのです。
背中を押してくれた出会い
迷っていた私の背中を押してくれたのは、立川で法定後見人の仕事をされている士業の方との出会いでした。
日々の業務の大変さを語る一方で、「本人の想いを大切にしたい」と真摯に話してくださる姿勢に、私は心を動かされました。
「こういう方が後見人になってくださるなら、お願いしてもいいかもしれない」
初めてそう思えた瞬間でした。
それは、かつて私が抱いていた「他人に任せる=冷たい」「本人の希望が通らない」というイメージとは、全く違うものでした。
制度が悪いのではなく、どう関わるか、誰に託すか。
その選択次第で、本人にも家族にも安心をもたらすことができる――そう思えたのです。
今、私にできること
結局、私は後見人になることを断念し、司法書士さんに申請手続きをお願いすることにしました。
申請は家庭裁判所に一任する形です。
そして今、私が一番感じているのは、
**「もっと早く準備しておけばよかった」**という後悔です。
叔母の診断書は、施設と病院の協力のおかげで思ったより早く整いました。
7月中旬には書類一式を司法書士さんに送りましたが、家庭裁判所に提出してから決定までには、さらに2〜3か月かかると言われています。
余命が限られた叔母にとっては、時間との戦い。
「間に合わないかもしれない」――その焦りと不安は、想像以上に大きなものです。
それでも、関わってくださっている皆さんが「何とか間に合わせよう」と動いてくださっている。
その気持ちが、どれほど私の支えになっているか分かりません。
相続対策は“今”から始めるもの
今回の経験を通して、私は改めて思いました。
相続や介護の準備は、「何かが起きてから考える」のでは遅いということ。
制度の仕組みを知ること、信頼できる人を見つけておくこと。
そして何より、
「私が支える側になろう」と思ったときに、
すぐ動けるようにしておくこと――
それは制度の仕組みを知り、信頼できる専門家とつながり、
必要な書類や意思確認を少しずつ準備しておくこと。
それが、支えたい人を本当に支えるということなのだと、今は感じています。
―――――――――――――――――――――――――
🌿【次回予告】
次回は、「親族間の合意形成」について。
さまざまな立場や感情を持つ家族の中で、どうやって気持ちがまとまっていったのか。
リアルなやりとりをお伝えします。
病と時間のはざまで、私たちは何を優先し、どう決断すべきなのか。
次回、「命のリミットと向き合うとき」——伯母の変化と、私の想いの揺れをお伝えします。
■相続やお金のことについて気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ おせっかいFPからのお知らせ ■□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】現在募集中のセミナー
「親に相続の話、どう切り出す?」
~わかりやすくてためになる 初めての相続セミナー~
【開催日時】
2025年8月22日(金)13時30分〜14時30分
【会場】
アキシマエンシス
昭島市 教育福祉総合センター
東京都昭島市つつじが丘3-3-15
202会議室
【交通アクセス】
・JR昭島駅北口 徒歩10分
・JR中神駅北口 徒歩10分
・立川バス「昭島市民会館」バス停 徒歩5分
・駐車場(有料)60台
・駐輪場 自転車 100台 / バイク 8台
【お支払方法】
・クレジット
・銀行振込
・会場での現金払い(但し、申し込みはウェブチケットから申込登録して頂きます。)
●ご連絡・問い合わせについて
HPの<お問い合わせ>から、または、メールにてお問い合わせをお願いいたします。
メールアドレス fumiko.7655@gmail.com
https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/08003369202521

⇒ ホームページURL