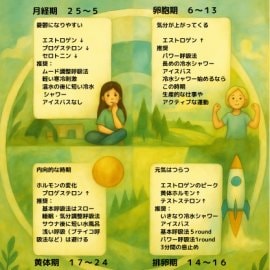2025.04.23
#029 第5の柱 トライブ
「早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行け」
(If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.)
アル・ゴア元副大統領がノーベル平和賞授賞式典の演説で引用し、有名になりました。2021年岸田首相の所信表明演説にも登場します。
昨年のキリマンジャロ登山で、モシという街に滞在しました。
タンザニアのルオ語の諺に、「若者はひとりでなら早く走ることができる。年寄りがいると遅くなる。けれども共に行けば遠くに行くことができる」(Alone a youth runs fast, with an elder slow, but together they go far)というものがあるそうです。こちらが起源だと思います。
私なりの解釈ですが、
ファーストペンギンのようなハイリスク・ハイリターンの勇者は、道を切り開きますが、最初の餌食になる事も多く、逆に、気が弱くてキャンキャン吠える犬(20匹に1匹くらい産まれるそうです)警報器のような役割を果たして群れを守っています。どちらも重要な役割で、群全体として、着実に進む組織になると思っています。
雪山登山のグループでは
・早く山頂に行きたい人
・ゆっくり景色を楽しみたい人
・体力に自信がない人
・お菓子ばかり食べている人
いろいろな人がいますが、その平均値のペースを守って移動するのが、余裕のあるメンバーが、遅い人を助けたり、チームとして機能しやすいような気がしています。
呼吸法も1人では10ラウンドも頑張れません。
実際に1人でやってみると、5ラウンドくらいで寝てしまう事が多いので、4ラウンド以上の呼吸法のセッションは海外では人気コンテンツです。呼吸法10ラウンドのみアイスバスなしで350$(約5万円)なんていうワークショップもあります。
また、雨の日に、滝に行くなんて、一人じゃそんな気分になれないですよね。
でも仲間が一緒なら、それは楽しい冒険になり得ます。
ヴィム・ホフ・メソッドの第5の柱なのか?
ポリヴェーガル理論では迷走神経を発生学的・機能的に「背側迷走神経複合体」と「腹側迷走神経複合体」の2種類に分類します。
安全安心を感じられる状況か、
危険を感じる状況か、
命の危険を感じる状況か
で3系統の自律神経系が切り替わって環境に対応するそうです。
周りが安全安心を感じる状態(心理的安全圏)だと腹側迷走神経複合体が働きます。哺乳類になってから獲得した新しい迷走神経で、「つながりをつくるための神経」と呼んでいます。群れると妙に強気になる事と関係があると考えています。
もう一つ”ピグマリオン効果”という、他の人からの期待を受けることで勉強や作業などの成果を出すことができる心理学的。
ピグマリオン効果の具体例としては、「”この子はデキる子です”と教師に教えてから指導させると”生徒の成績が本当に上がった”」ということです。
ワークショップを例に説明すると、
大前提として、私は人類全員にものすごいポテンシャルが眠っていると信じています。参加者の皆さんが自分を信じきれなくても、私だけは皆さんのポテンシャルを心の底から信じています。
実は、私だけではなく、ワークショップを頻繁に開催している会場の関係者などは、アイスバスの様子を何度も見ているので、「あの超ビビってる人も、結局できちゃうのよね~」などと感じています。
「私がこの人にはものすごいポテンシャルがある」という目で参加者を見ていると、参加者の方にも「自分はできる人間だと思われている」となんとなく伝わります。すると、実際にアイスバス10分くらいなら難なくこなせてしまうのです。
ヴィム・ホフ・メソッドの大きなテーマとして、自然環境との調和がありますが、自分が所属するコミュニティも環境の一つ。人目があると勉強が捗ったりしますが、周りの人の良い影響を受けて、楽しくアイスバスに入れたら、それは一人で逡巡しているよりは、ずっといいですよね。
ホモ・アークティカス(Homo Arcticus)は社交的という動画がありますが、周囲の人という環境とも馴染み、調和していけたら、人生はもっと楽しくなるでしょう。