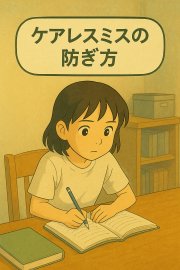国語力を磨く:物語問題の正しい解き方
はじめに:物語を読むことと問題を解くことは違う
国語の読解問題、特に物語問題の解き方について話をしていきます。まず理解すべき重要なポイントは、「物語を読む」ことと「物語問題を解く」ことは全く異なるということです。この二つをごっちゃにしていると、成績は伸びません。
よく国語の先生は「読書をしなさい」「問題を解きなさい」とアドバイスします。あるいは「国語はセンスだから」と言って、受験直前まで放置することもあります。しかし、国語にも解き方の公式やルールが存在します。
それを理解して実践するだけで、成績は必ず上がります。多くの生徒が国語で躓くのは、この基本的な考え方の違いを理解していないからなのです。
物語と物語問題の根本的な違い
物語を読む楽しさ
物語は時系列で最初から読み進め、背景情報が分かります。例えば「幼馴染との関係」など、人物関係や状況が理解できる状態で読みます。物語を読む楽しさは感情移入にあります。登場人物に共感し、「ドキドキする」「悔しい」「腹立つ」という感情を持つことが読書の醍醐味です。
これが本来の読書の楽しみ方であり、「物語を読む」ということです。
物語問題の特性
一方、物語問題は文章の途中を切り取り、時間内に解かなければなりません。背景情報がほとんど分からないまま判断しなければいけないのです。
例えば、登場人物がどのような生い立ちなのか、どのような関係性なのかが分からない状態で問題を解くことになります。
だからこそ、物語問題を解く際には感情移入してはいけません。必要なのは「観察」です。感情移入ではなく、冷静な観察と論理的な判断が求められます。
この点が多くの生徒や、時には指導者も誤解している部分です。
なぜ感情移入では点数が上がらないのか
よく見られる間違った指導法として「登場人物の気持ちになりなさい」というものがあります。しかし、この方法では子供の点数は上がりません。
なぜなら、他人の気持ちは基本的に分からないからです。立場が違えば感情は全く理解できないことがあります。
例えば、母親は子育てを経験して初めて自分の親の気持ちが分かるようになります。小学生の子供に「戦争に行くお父さんの気持ちを理解しなさい」と言っても、その経験がない子供には理解できません。
実際のデータからも、国語の点数が良い時と悪い時があるのは物語問題の点数の開きによるものが大きいことが分かっています。
例えば、中学生が主人公がバスケットボールのキャプテンで恋愛話などの内容の時は点数が高く、お父さんが戦争に行くような物語の時は点数が低くなる傾向があります。
これは自分の感情というフィルターを通して考えるため、自分が想像できる登場人物の時は点数が取れますが、想像できない登場人物の時は点数が下がるからです。
正しい解き方:3つのチェックポイント
物語問題で登場人物の心情を問う問題は頻出です。こうした問題を解くには3つのポイントをチェックします。これらは文章中に必ず根拠として存在しています。
1. 動作・表情から判断する
登場人物がどのような動作をしたか、どのような表情を見せたかに線を引きます。これが感情を判断する重要な手がかりとなります。
例えば「のび太は唇をぐっと噛み、拳を握りしめて泣き出した」という描写があれば、単に「ジャイアンに殴られたから泣いた」という表面的な理解ではなく、動作(唇を噛む、拳を握りしめる)から「悔しくて泣いた」と判断します。動作や表情から感情を読み取ることで、より正確な心情理解につながります。
2. セリフから判断する
登場人物のセリフは心情を判断するヒントになります。ただし、セリフがそのまま本心を表しているとは限らないことに注意が必要です。
例えば、小さなマンションに住んでいる人の家にお金持ちの子が来て「すごい大きな家だね」と言った場合、それが本当に感動しているのか、あるいは皮肉や嫌味を言っているのかは、文脈から判断する必要があります。セリフを単独で見るのではなく、前後の状況と合わせて考えることが大切です。
3. 情景描写から判断する
情景描写は「感情」と「景色」を組み合わせた言葉です。「情」は感情の情、「景」は景色の景であり、登場人物の感情を通して見る景色を表します。
例えば「ドアを開けると、周りにはどんよりと雪が横たわっていた」という描写は、登場人物の気持ちが落ち込んでいることを示します。
雪自体は色がないのに「どんより」と描写されるのは、登場人物の感情が投影されているからです。逆に「キラキラと輝く雪が一面に横たわっていた」なら、登場人物が明るい気持ちであることが分かります。
情景描写を通じて登場人物の内面を読み取ることで、直接的な描写がなくても心情を理解することができます。
成績向上のための具体的な学習方法
根拠を探す訓練をする
国語問題を解く際に最も重要なのは「なぜその答えになったのか」という根拠を探す訓練です。算数では途中経過を確認して「ここが間違っている」とチェックするように、国語でも論理的に根拠を見つける練習が必要です。
例えば、方程式で「-3を移行したら+3になる」というように、算数では間違いを特定して修正することができます。国語でも同様に、「なぜこの答えが正しいのか」「どの部分からそう判断できるのか」という根拠を明確にすることが大切です。
問題集を解いて解説を読み、自分の解答と模範解答の違いを理解し、どこがどう違うのかを自分で修正していく習慣をつけましょう。サイコロを振るようななんとなくの解き方ではなく、論理的に解き方の根拠を導き出していく形で取り組まないと、成績は上がりません。
解き直して人に説明する
問題を解いた後、解説を読んで間違いを修正し、さらにそれを人に説明できるレベルまで理解を深めることが大切です。例えば、子供に問題を解かせた後、解説を見せて答え合わせをさせ、「なぜこうなったのか」「どこが間違っていたのか」を説明させる練習が効果的です。
「この部分がこう解釈できるから、こういう答えになる」と説明できるようになれば、確実に力がついていきます。これは算数で「-3を移行するときに+3にするのは間違いだった」と説明できれば、次回からは正しく解けるようになるのと同じ原理です。
この「説明する」という過程を通じて、解き方が本当に身についているかどうかを確認することができます。また、間違いを直すことで学びが定着していきます。
実践的なアプローチ:観察と分析の重要性
物語問題を解く際には、日常生活での人間観察の経験が役立ちます。例えば、いつもニコニコしている友人が突然「帰ろうか」と言ってプイッと行ってしまったら、「何かあるな、怒っているのかな」と判断できます。これは日頃からその友人を知っているからこそ可能な判断です。
しかし、初めて会う人の場合、同じ行動を見ても「元々そういう性格なのか」「その時だけ機嫌が悪かったのか」判断できません。物語問題も同様で、限られた情報から登場人物の性格や心情を判断しなければならないのです。
だからこそ、敬語を使い分けるように、「物語を読む時」と「物語問題を解く時」で頭を切り替える必要があります。物語問題を解く時には、感情移入せず観察して理性的に判断する姿勢が重要です。
まとめ:物語問題攻略の要点
国語には解き方があります。物語を読む時は感情移入しても良いですが、問題を解く時は感情移入せず、観察と分析が必要です。
物語問題を解く際の重要ポイントをまとめると:
- 「物語を読む」と「物語問題を解く」は別の思考法が必要
- 登場人物の心情を把握するには、動作・表情、セリフ、情景描写の3つをチェック
- なぜその答えになるのかという根拠を常に考える
- 解き直した後は人に説明できるレベルまで理解を深める
- 感情移入ではなく観察と分析で問題に取り組む
これらのポイントを意識して学習することで、国語の物語問題における成績向上につながります。国語は「センスの問題」ではなく、論理的に解ける科目です。正しい解き方を身につければ、誰でも成績を上げることができます。
問い合わせ・ご相談はこちらから