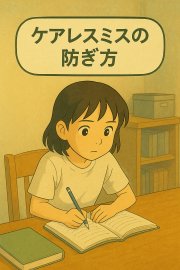2025.03.14
細分化で解決!子どもの学習問題
学習に悩む親子のために、長期的に役立つ考え方をご紹介します。問題解決の鍵は「細分化」にあります。大きなステーキを一度に食べないように、学習の問題も細かく分解して対処していきましょう。
「できない」の正体を見極める
「うちの子、国語ができないんです」という相談をよく受けます。でも「できない、できない」と言うだけでは状況は改善しません。実はその裏には「やらない」ではなく「やれない」という真の問題が隠れていることが多いのです。
私が塾で指導していた時の話です。中学生のクラスがとてもうるさく、授業にならないほどでした。最初は怒ってばかりいましたが、ある時気づいたんです。その子たちは「やらない」のではなく、「やれない」から騒いでいたんです。レベルが合っていなかったんですね。
そこで簡単な計算問題を出し、「テストするよ、一番ビリだった子は宿題いっぱい増やすからね」と言いました。すると、問題が難しくないからか、みんな必死で集中して解き始めたんです。教室はシーンと静かになりました。
大切なのは、子どもが「なぜできないのか」を冷静に見極めることです。塾で落ちこぼれているからダメなわけではなく、単にレベルが合っていないだけかもしれません。高跳びで例えるなら、1メートルしか跳べない子に1.7メートルを跳べと言っても無理なのと同じです。
国語力アップの具体的方法
国語の成績を上げるには、まず「知識問題」と「読解問題」に分けて考えましょう。偏差値55を切っている子は、多くの場合「知識問題」ができていません。漢字の読み書き、語の意味、文法などの基礎知識です。
「うちの子、漢字はまあまあできてます」というお母さんもいますが、満点ですか?と聞くと違うんですよね。特に漢字の読みは読解に直結します。早めにマスターすべきなんです。
実際にあった例ですが、ある子が「のび太君が塀を飛び越える時の気持ち」という問題で、文中の該当箇所に線を引いて準備はできていたのに答えられませんでした。なぜか?「立ち尽くす」という語の意味が分からなかったからです。これでは教科書が黒塗りのような状態で読んでいるようなものです。
時間配分の重要性
国語のテストで「時間が足りない」という悩みはよく聞きます。実際、あるテストで60分を70分に延長したら、その子の成績が上がったことがありました。つまり、時間があれば解ける問題だったんです。
どうすれば読解の時間を増やせるか?知識問題にかかる時間を短縮することです。例えば漢字問題に15分かけていたのを10分で解けるようになれば、浮いた5分を読解に回せます。まずは知識問題を完璧にし、解く時間を短くする。そうすれば自然と読解に使える時間が増えるんです。
正しい解き方を身につける
偏差値50を超えたら、次は読解問題の「正しい解き方」を身につけることが大切です。特に国語は解き方を教えていない塾も少なくありません。親も「どう教えていいか分からない」と悩んでいるでしょう。
よく「登場人物の気持ちになりなさい」とアドバイスするお母さんがいますが、これだけでは不十分です。なぜなら、自分と環境が似ている場合は想像できても、全く違う立場の人の気持ちは想像できないからです。例えば、いじめられっ子ならのび太の気持ちは分かるかもしれませんが、ジャイアンの気持ちは分からないでしょう。
正しい解き方は、表情・行動、セリフ、情景描写に線を引き、その中から考えることです。「なぜそう考えたのか」を「本文のここにこう書いてあるから」と説明できるようにします。感覚的に解くのではなく、論理的に解く習慣をつけるのです。
論理的思考への切り替え
国語の上達が難しいのは、普段使っている日本語から「論理的な日本語」への切り替えが必要だからです。これは敬語と似ています。普段「お母さん、ご飯!」と言っている子も、電話がかかってきたら「母は今おりません、呼んできます」と切り替えられますよね。
例えば志望動機を聞かれたとき、グダグダと話すより「私が○○中学を志望する理由は3つあります。1つ目は…、2つ目は…、3つ目は…です」と論理的に説明する方が伝わります。この切り替えを身につけるまで、徹底して練習することが大切です。
学習の問題は細分化して対処すれば、必ず解決の糸口が見つかります。子どもたちの可能性を信じ、一歩一歩着実に力をつけていきましょう。