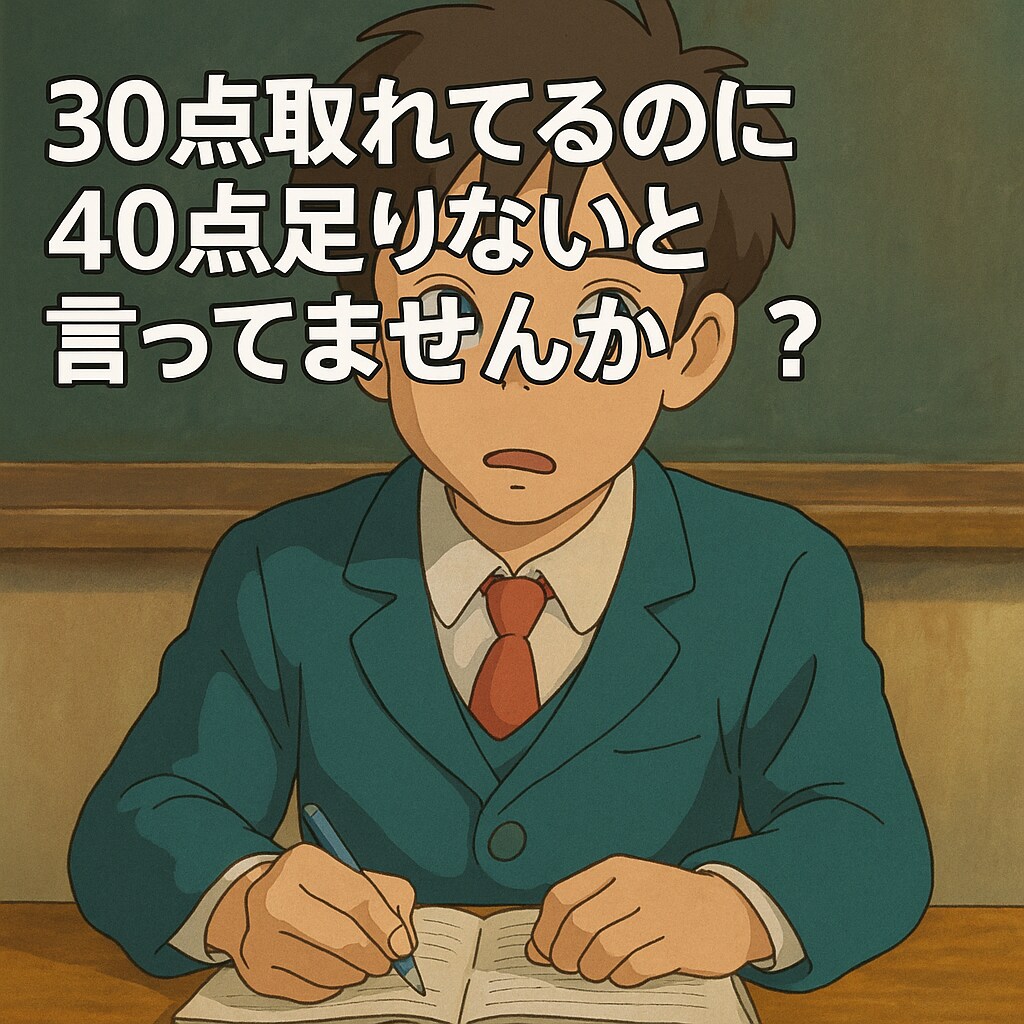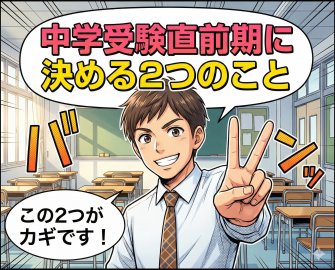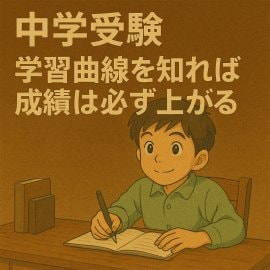2025.10.26
30点取れているのに40点足りないと言っていませんか?
受験生を抱えるお母さんにとって、子どものやる気の問題って切っても切れないですよね。
もちろん自分からやるお子さんっていうのはいるんですけども、やる気を起こすっていうのはどういう時に起こるかって考えると、実は自分のやっていることに結果が出るとやる気が出るんです。
じゃあ結果が出てない時どうするのか?
結果が出てるのをこちらがフィードバックしてあげるんです。
もしかして、あなたもこんなことをしていませんか?
- 合格点70点のうち30点取ったのに「あと40点足りない」と言ってしまう
- できてないところばかり指摘してしまう
- 「なんでこんな問題も間違えるの?」と言ってしまう
- 子どもが勉強しても褒めない
- 塾に行っているだけで「勉強してない」と思っている
これが、子どものやる気を失わせる親の共通点です。
なぜなら、できてるところを見ていないからです。
私の自己肯定感が低かった理由
実は私、コンサルタントをしてた時に心理テストをしたんですよね。
で、心理テストをした時に結果がどうなったかというと、非常に自己肯定感が低いって言われたんです。
「え、自己肯定感が低いのかな?」って、まあ結構見た目がこう元気よくやってるから「そんなことないじゃないの?」って思うかもしれないですけど。
で、そのコンサルタントの人に話を聞いたところ、「いや、多分あなたは目標が高いからじゃないですか」って。
目標が高いと、自分ができないってなるじゃないですか。
100点を目指すと50点でもできないと思う
例えばですね。
すごく難しいテストで、学年の平均点が10点とします。
で、100点を目指してて、例えば50点取ったら、平均点10点で50点だからかなりできてるじゃないですか?
でも100点を目指してたら、「ああできない」ってなるじゃないですか?
という風に、私の場合はですね、目標がいつもかなり高いんですよ。
だから自己肯定感が低くなるんですよね。
70点と40点の見方
これ、目標達成の時の常套手段なんですけど。
例えば100点満点で、合格点が70点だったとします。
で、今30点だとするですよね。
そうすると、ついつい差の40点のところに目が行きがちなんですね。
で、それ自体は、そのできてない40点を目にしてそれをできるようにしないといけないっていうこと自体は間違っていないんですよ。
なんだけど、もうちょっと大事なことは、それと同時に30点も同時に見るっていうことが大事なんですね。
どういうことかって、できてるところも見ないといけないんですよ。
人間って、できてるところは必ずある
あの人間って、勉強してたら全部が全部できないわけじゃなくて、できてるところってあるんですよ。
通常は。
で、「いや成績が出てない」っていう人でも、一般のお子さんに比べたらやっぱり例えば受験やってる子、中学受験なんかやってるから、特にできてるんですね。
普通の公立の学校の子に比べたら。
でも、それを置いといて、できないところばっかり指摘するんですよ。
そうすると、やる気がなくなるんですよね。
私が意識していること:できてるところを伝える
で、私がその意識して指導する時にやってるっていうのは、実際にできてるところは「できてる」っていう風に伝えないといけないんですよ。
というのは、人間ってどっちかというとできてないところに目が行きがちだから。
特に親はそうなんですよね。
親御さんっていうのは子どもに対して期待がすごく高いと、高いからできてるところばっかり、できてないところだけ目につくんですよ。
で、ましては受験だったらね。
「70点であと40点足りない、どうすんの?40点も足りないから」
「ここもできてない、ここもできてない、ここも早く」って言うんだけど。
でも、70点のうちに30点も取れてるっていう事実があるわけじゃないですか?
それは事実ですよね。
だから、「いや、30点はできてるよ。30点はできてるから。じゃああと何点あげようか」っていう。
その30点を認めてから、できてないところをやるっていう形にするんですよね。
これは褒めてるんじゃなくて事実
これ、褒めてるんじゃなくて事実なんですよ。
だから事実の指摘が偏ってるからですよね。
で、もっと言うと、偏るんであれば、できてるところはもうちょっとこちらの方から指摘してあげるっていうことが、すごく大事なんですよね。
なぜかって言うと、それが前に進む原動力になるからなんですよ。
結果が出てない時の指導が1番辛い
人ってね、私なんか何が1番辛いかって言うと、結果が出てない時の指導なんですよね。
それ、お母さんもこれ、仕事でもね、お父さん、お母さんも分かると思うんですけど、仕事でやってて何かやってても認められないとか報われないとか、辛いことがないですか?
これ辛いと思うんですよ。
それは大人であろうが関係ないんだけど、子どもであればなおさらその辛いんですよね。
だから、やってることに結果が出てることをちゃんと伝えないといけないんですよ。
10問中5問正解の場合
で、私もそうだけど、例えば10問中5問正解だったと。
「5問しか取れてない」
いや、「5問取れてるね。ここと、ここと、ここはできてるよね。例えば計算問題はできてるよね? 例えば図形の問題はできてるよね。でもこれはできてないよね」
っていう風に、できてるところをちゃんと指摘してあげることなんですよね。
不登校の子の指導で気づいたこと
なんでこんなことを言うようになったのかというと。
私は不登校の子も指導してたんだけど、不登校の指導する時にやってたのが、まあ不登校の子ってなかなか動けないんですね。
動かないというか、動けないんですよ。
本人もやる気があって行きたいと思ってたとしても行けないと。
じゃあどうするかって、動かさないといけないですよね。
行動しないといけないんだけど、まず行動できないんですね。
そういう子っていうのは。
で、なんでかって言うと、自分自身の自己肯定感を下げて、できないと思ってるからできないと思ってるからですよね。
じゃあどうするか?
実はできてるところを指摘するんです。
「私、こんなにやってるやん」
これ、あの子どもに言ったんだけど、「じゃあやったことを書いてみて」っていう風にこう、毎日ね。
学校行ってないけど、やったことを書き出すと、**子どもなんて言ったかっていうと、「私、こんなにやってるやん」**っていう風になったんですよね。
実はやってるんですよっていう形ですね。
そうするとですね、自分の自己肯定に繋がっていくんですよ。
私が毎日やってる4つの質問
実は私が毎日やってることの中でね、4つあるんですけど:
- 今日良かったことは何ですか?
- もしやり直すとしたらどうしたらいいんですか?
- 明日最も重要な仕事は何?
- その重要なために何をする?
この4つの質問を毎日書いてるんですけど、その中で**1番最初に行くのは「良かったことは何」**っていう風に、自分の良かったことを見つけるってことをしてるんですよね。
で、そうしないと人生楽しくないじゃないですか?
親が意識して指摘してあげる
で、大事なのは、それを親が意識して指摘してあげるってことなんですよ。
で、「褒める」っていうと、なんか褒められないわけじゃなくて、あの、認めるってことなんですよね。
例えば、「塾にでもうちの子勉強もしてないし、塾行ってるだけよ」って言うかもしれないですけど、塾行ってるだけって言っても、頑張ってるんですよ。
例えば、私が奈良で塾をした時に、「塾に行きます」って言っといて、家出てるのに塾に来なかった子もいるんですよ。
どこ行ってたかって、ゲームセンターに。
それ高校生なんですよね。
そういう子もいたんですよ。
だからね、本当に塾に行くだけでも頑張ってるって事は認めてあげて、それをこうフィードバックしてあげるってことが、1つはやる気に繋がるのかなと思ってます。
小さい変化でもフィードバックする
小さい変化でもできてるようになってたら、それをフィードバックする。
それが1つのポイントかなと思ってます。
あなたへのメッセージ
受験生を抱えるお母さんにとって、子どものやる気の問題って本当に切実ですよね。
でも、やる気が出ない原因は、できてないところばかり指摘されているからかもしれません。
私も自己肯定感が低かったんです。目標が高いから、できてないところばかり見てしまって。
でも、不登校の子の指導を通じて気づいたんです。
できてるところを指摘することが、やる気に繋がるって。
合格点70点のうち30点取ったのに「あと40点足りない」と言うのではなく、**「30点取れてるね。じゃああと何点あげようか」**と言ってあげてください。
これは褒めてるんじゃなくて、事実なんです。
小さい変化でもフィードバックする。それが子どものやる気を引き出す1つの方法です。
ぜひとも、できてるところを見てあげてくださいね。
学習ジム・コーチ 堀