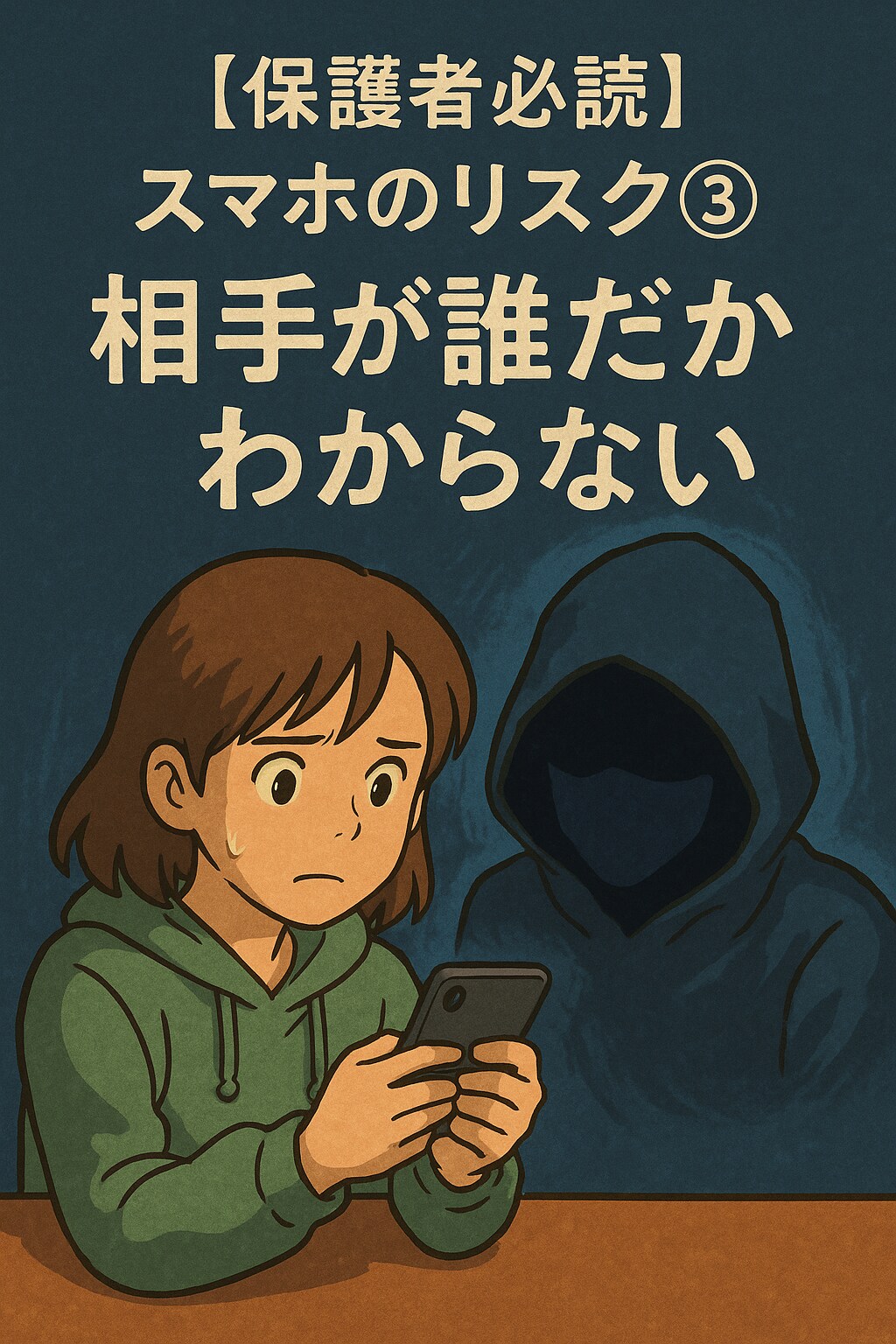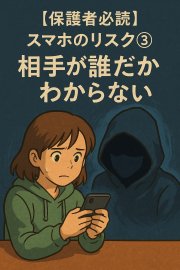2025.10.18
【保護者必読】スマホのリスク③相手が誰だかわからない
お子さんにスマホを持たせている保護者の方へ。
「うちの子は大丈夫」
そう思っていませんか?
スマホは便利です。世界中の情報にアクセスでき、遠く離れた人とも簡単につながれる。
でも、その便利さの裏には、お子さんを危険にさらすリスクが潜んでいます。
それは「相手が誰だかわからない」ということです。
ネット越しでは本性が見えない
インターネットを介すると、相手の本当の姿が見えなくなります。
自動車の免許を取るとき、最初に事故の映像を見せられますよね?
便利な自動車にもリスクがあるように、スマホにもリスクがあります。
特に気をつけるべきは、「常識が通じない人」と簡単につながってしまうことです。
私が電話面接を必須にしている理由
私のオンライン塾では、体験の前に必ず電話面接をしています。
これには3つの理由があります:
- 親御さんに安心してもらう
- お子さんの状況を知る
- トラブルになりそうな相手を事前にお断りする
「せっかくのお客さんを断るなんて...」
そう思われるかもしれません。
でも、長年この仕事をしていると、「この家はトラブルになりやすい」というのが分かるようになるんです。
25年前の苦い経験
私がインターネットビジネスを始めたばかりの頃、こんなことがありました。
メールのやりとりは丁寧で、文章も普通でした。
でも、電話で話したときに「嫌だな...」という感じがしたんです。
その予感は的中しました。
その方は:
- 夜中の12時に酔って電話してくる
- 誰かと常に揉めている
- 私が指導中でも電話がなりっぱなし
何時間も電話で話しても解決せず、電話代は月6万円に...
結局、その方との関係は終わりましたが、他の人から聞いた話では、別の所でも同様のトラブルを繰り返していたそうです。
電話したときの印象では「やくざまがい」の方でした。
これは決してメールだけでは判断できないことです。
文章と本人は違う?
ネットでよくあるのが、「文章と本人のギャップ」です。
ケース1:がっかりした例
あるセラピストの方のブログを読んで感動しました。
「相手の良い所を見つけましょう」と素晴らしいことを書いている。
「この人に会ってみたい!」
そう思って実際に会って食事をしたら...がっかりです。
話す内容は:
- 「私の知っている○○さんはダメ」
- 「△△さんはあの人はどうしょうもない」
悪口ばかりでした。
思わず「違うやん」と突っ込みを入れたくなりました。
ケース2:意外と良かった例
逆に、ブログの内容が毒舌で「この人は避けた方がいい」と思っていた人が、会ったら「ムチャクチャ紳士的」ということもありました。
だから、私も良い人なんて思わないでください(笑)
私も電話をしたら「文章とは違う」とよく言われます。
匿名の怖さ
18年もこの仕事をしていると、いろいろなことがあります。
休みの日のメルマガ
以前は休みの日はメルマガをお休みにしていました。
すると、「休むなんて信じられない」という非難のメールが届きます。
もちろん無料なので、そんな義務はないのですが...
同業者のスパイ行為
今では普通に「塾の先生の子どもを指導する」ということをしています。
塾の先生も正直に「実は家では塾をしているのです」と話してくれます。
生徒の集客の相談にのることもあります。
ですが、以前は「自分の素性を語らず、偽名で申し込む」ことがあったのです。
例えば:
- 体験で「山田太郎」という名前で申し込み
- そのアドレスを調べてみると「山川太郎」で塾をしていた
- 住所が途中までしか書いてない
- 指導していて「無料ではなかったのですか?」とお金を払わない
こんなこともありました。
子どもが巻き込まれる危険
中学生では「出会い系」を使う子もいます。
以前聞いた話では、出会い系で社会人の人と会っている子もいました。
実際のニュース事例①
北海道で、SNSを通じて知り合った10代前半の少女に乱暴した疑いで、埼玉県の25歳男が逮捕されました(2025年10月3日・産経ニュース)。
当時男が住んでいた函館で、SNSを通じて知り合ったとみられています。
実際のニュース事例②
熊本県で、女子生徒のわいせつ動画を撮影させ販売した疑いで、20~30代の男女が逮捕されました(2025年10月2日・TBSNEWSDIG)。
実際のニュース事例③
宮崎県都城市で、中学生(15歳)が大麻所持の疑いで逮捕されました(2025年10月2日・TBSNEWSDIG)。
ネットを通じて大麻を入手したとみられています。
いずれも、SNSやネットが関係しているのです。
結論:保護者ができること
自動車の免許を取るとき、最初に事故の映像を見せられますよね?
便利な自動車にもリスクがあるように、スマホにもリスクがあります。
お子さんを守るために、保護者ができることは:
- リスクを知っておくこと
- お子さんに具体的な事例を使って危険性を伝えること
- 「ダメ」と禁止するだけでなく、「なぜダメなのか」を理解させること
もちろん、スマホにはメリットもたくさんあります。
でも、リスクを知った上で使わせることが大切です。
それさえ頭に入れておけば、あとは良いことだらけです。
FAQ:保護者からよくある質問
Q1. 子どもにネットの危険性をどう伝えればいいですか?
A. 具体的な事例を使って説明することをお勧めします:
- 実際のニュース事例を見せる
- 「相手が誰だか分からない」ことのリスクを説明
- 個人情報を教えないことの重要性
「ダメ」と禁止するだけでなく、「なぜダメなのか」を理解させることが大切です。
Q2. スマホを持たせないほうがいいでしょうか?
A. スマホ自体は便利なツールです。問題は「使い方」です。
- フィルタリング機能を設定する
- 使用時間を決める
- どんなアプリを使っているか把握する
- 定期的に会話する
完全に禁止するより、正しい使い方を教えることが重要です。
Q3. 子どもが知らない人とSNSでやりとりしているようです。どうすればいいですか?
A. まず、頭ごなしに怒らないことが大切です:
- 「誰とやりとりしているの?」と優しく聞く
- 相手が本当に安全な人か一緒に確認する
- オフラインで会う約束をしていないか確認
- 個人情報(住所、学校名、本名など)を教えていないか確認
お子さんが「隠す」ようになると、かえって危険です。
Q4. うちの子は大丈夫だと思うのですが...
A. 「うちの子は大丈夫」と思っている保護者の方のお子さんほど、実は危険なことがあります。
理由は:
- 保護者が無関心だと、子どもは誰にも相談できない
- 何か起きても「怒られる」と思って隠す
- 危険な状況に気づかない
オフラインだったら「この人はやばそう。近づかないでおこう」と思うのが、ネットを介するとそれが甘くなります。
「誰かわからない」というのが一番怖いのです。
定期的にお子さんと会話し、何かあったら相談できる関係を作っておくことが大切です。
学習ジム・コーチ 堀哲嘉