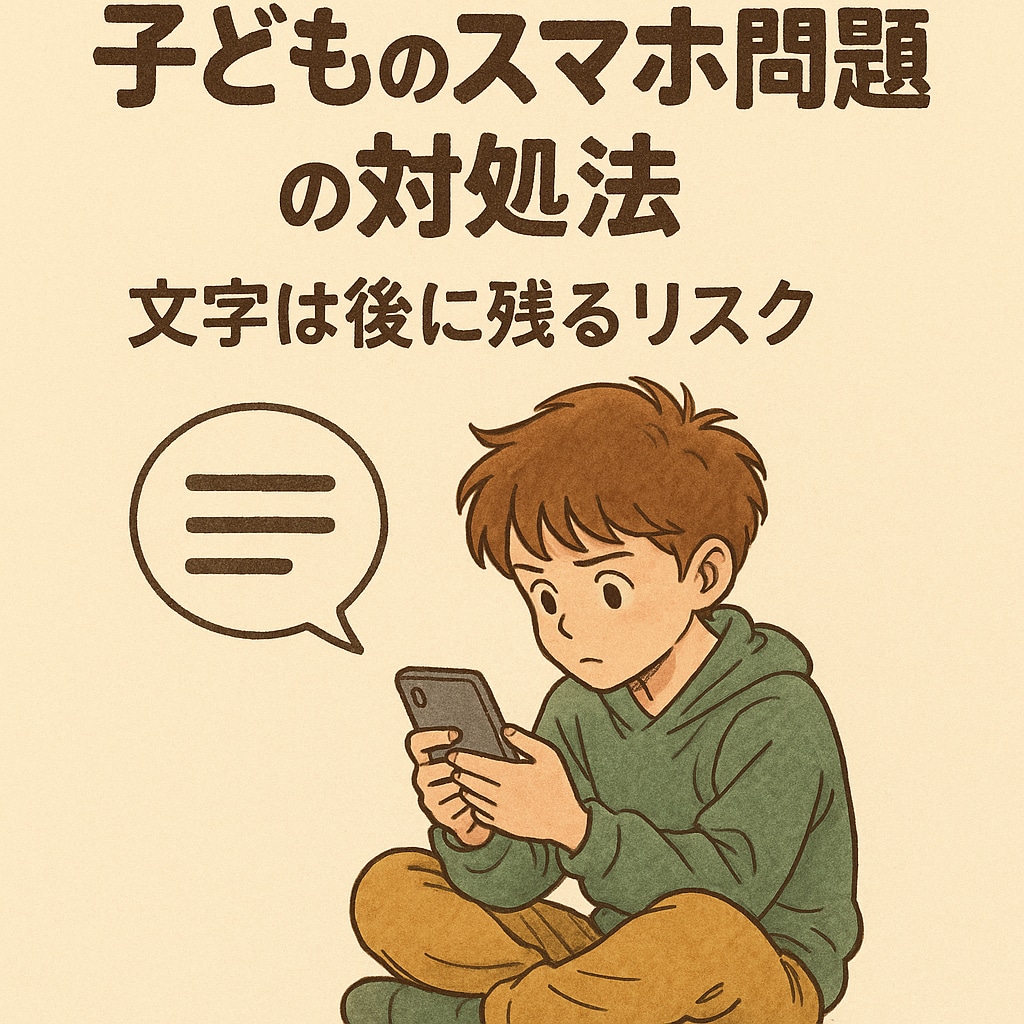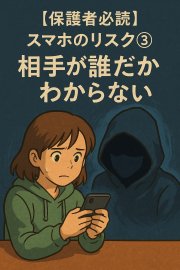2025.10.17
子どものスマホ問題の対処法 - 文字は後に残るリスク
前回の記事: 子どものスマホ問題の本質 - 一生続く自己管理の問題
昨日の続きです。
スマホを使うにあたってやるべきことは、大きく分けて2つです。
- スマホに関する情報を伝える
- スマホを使うルールを決める
今日は、1つ目の「スマホに関する情報を伝える」についてお話しします。
スマートフォンの問題はその中毒性
スマートフォンの問題は、その中毒性です。
その原因は、インターネットでつながっているからです。
ゲームだけでも問題ですが、さらにインターネットでつながっているので、リスクは必ず伴います。
だから、最初に「スマホ」に関するリスクについて話をしないといけないのです。
スマホのリスク:後に残ること
これって結構大変なことです。
実際に私は毎日授業報告書を書いていますが、書いているときは大変神経を使います。
それは残ってしまうからです。
なぜ「後に残る」ことが問題なのか
少し話をしましょう。
友達と話をしているときに、何気なく話をしていることや暴言でも、そのとき限りのことが多いです。
本人が軽い気持ちでも、後に残ります。
例えば、「お前は頭が悪い」と言ったとします。
このときは言ったのは「1回」です。
これをメールで送ったら、送った方は「1回」でも、もらった本人は削除しない限り何度も見ます。
仮に「10回」見たら、受け取った本人にとっては**「10回」言われたと同じこと**です。
当然ですが、「10回」も言われたら怒り心頭になります。
そして、喧嘩になります。
本人は軽い気持ちのつもりでも
本人は軽い気持ちのつもりでも、相手は必ずしもそう思わないかもしれません。
これは掲示板でもそうです。
残るという行為は、相手にもダメージを残すのです。
こんな風に書くと「何をオーバーな」と思うかもしれません。
それでは、実際にあった話をしましょう。
実例1:Facebookでの誤解
私の場合は、以前から私のメルマガを取っていた人とFacebookでつながりました。
それまでも何度かやり取りをしていましたが、歌手の飛鳥が「麻薬」で捕まったときのことです。
その記事を引用していました。
そしてそこにこんなことを書いていました。
「堀さんのように苦労をしていない人は麻薬にはまります」
ということを書いていたんです。
正直に言うと、**「この人は何を言っているのか?」**と。
今まで特に問題なくやり取りをしてきたので「?」です。
私の本当の経験
当たり前ですが、私の場合は独立して1人で何年もやってきて、普通のサラリーマンよりは何倍も大変な経験をしてきました。
途中で兄をなくし、家族が癌になり、それを乗り越えてきました。
決して「楽してきたわけではない」のです。
それに私はどちらかというと「健康オタク」に近いくらいで、今までもいろいろな健康食品を試していますし、今も健康食品を摂っています。
それに、たばこもやらないし、お酒もコントロールしているので、20年以上休みなく働いています。
それなのにそんなことを書かれたのです。
もちろん、その人との関係はそれでジエンドです。
実例2:コンサルタントの報告書
さらにこんなこともありました。
以前に私はコンサルタントから聞いた話です。
あるコンサルタントが顧問先の企業診断をしたときです。
企業診断というのは、会社の内容をお金や人、組織などあらゆる角度から分析して報告書を出して、相手の企業の改善を促すものです。
そこで、そのコンサルタントは良かれと思って、その会社の良いところと改善点を書きました。
もちろん、良かれと思ってやったことです。
相手の会社も報告書をもらったときは、「こんなたくさんのご指摘を受けてありがとうございます」と言って喜んでいたそうです。
ですが、何日後、その会社の社長が電話で怒鳴り込んできたのです。
その内容は「報告書の指摘」についてです。
改善点として書いたことが、相手にとっては悪口ととらえられて、がまんならなかったのです。
そのときは良くても、**「あとに残すと大変なことになる」**という例です。
実例3:くら寿司の迷惑動画で人生が変わった女子高生
最近、こんな事件がありました。
2025年10月中旬、大手回転寿司チェーン店『くら寿司』の山形南館店で、女子高生が迷惑行為を行う動画がSNS上で拡散されました。
動画の内容:
- 回転する寿司を素手で触ってレーンに戻す
- しょうゆ差しから直接自身の口に流し込む
- ラーメン店で素手でラーメンを食べる
女子高生は、インスタグラムのストーリーズだけでなく、『BeReal』というSNSでも投稿していました。
そして、位置情報を公開していたため、店舗が特定されました。
さらに、迷惑行為を行った女性だけでなく、撮影者まで名前や学校名が特定される事態になったのです。
面白半分のつもりが取り返しのつかないことに
くら寿司は公式サイトで怒りをあらわにし、こう発表しました。
「今回のような行為につきましては、多くのお客様にご利用いただく飲食店として、許される行為ではなく、厳正な対応をしていく予定です」
実行者についてはすでに特定しており、地元警察に相談しながら対応を進めると。
ネット上では:
- 「こういうバカっていなくならないんだよね」
- 「何が楽しいの?の一言に尽きます」
- 「特定してちゃんと賠償請求するべき。若いからで済まされる事じゃない」
という厳しい声が上がっています。
スシローの事例:6700万円の損害賠償請求
参考までに、2023年1月末、『スシロー』でしょうゆ差しを直接舐めた少年の動画が拡散されました。
スシローは、この少年に約6700万円の損害賠償を求めて訴訟を起こしました。
(その後、同年7月に訴えは取り下げられましたが、この金額が請求されたという事実は重いです)
「未成年だから」は通用しない
ネット上では、「未成年だからと言って許される行為ではない」「今後のためにも厳格な対応をするべき」という意見が多く上がっています。
本人たちは「軽いノリ」「冗談」「その場の雰囲気」でやったことでも、後で取り返しのつかないことになるのです。
お子さんに教えるべきこと
これらの例から、お子さんに教えるべきことは:
文字は後に残る。だから慎重に。
口で言った言葉は消えますが、書いた文字は消えません。
送った側は「1回」のつもりでも、受け取った側は何度も見ます。
軽い気持ちで書いたことが、相手を深く傷つけることがあります。
まとめ:スマホのリスクを教える
スマホを持たせる前に教えるべきこと:
スマホのリスク:
- 文字は後に残る
- 送った側は1回、受け取った側は10回見る
- 軽い気持ちでも相手は深く受け取る
- 書いた内容は取り消せない
教えるべきこと:
- 書く前に一度考える
- 相手がどう受け取るか想像する
- 怒っているときは書かない
- 悪口や暴言は絶対に書かない
保護者ができること:
- 実例を話して聞かせる
- 「後に残る」ことの怖さを教える
- 自分(親)も気をつける姿勢を見せる
具体的な対策:
- スマホを持たせる前にリスクについて話す
- 「送信する前に一度読み返す」ルールを作る
- 親子でスマホの使い方を定期的に話し合う
あなたはお子さんに、「文字は後に残る」というリスクを教えましたか?
スマホを持たせる前に、必ずこのリスクについて話してください。
軽い気持ちで送ったメッセージが、友達との関係を壊すことがあります。
それを防ぐために、親ができることは「知識を与える」ことです。
次回は、2つ目の「スマホを使うルールを決める」についてお話しします。
よくある質問
Q. 子どもに話しても「わかってる」と言われます。どうすればいいですか? A. 「わかってる」と言っても、実際の事例を知らないことが多いです。この記事のような具体例を話してみてください。リアルな話は心に残ります。
Q. 親の私も、過去にSNSで失敗したことがあります... A. それは逆に良いチャンスです。親の失敗談を話すことで、お子さんはより真剣に聞いてくれます。「お母さんもこんな失敗をしたから、あなたには同じ失敗をしてほしくない」と伝えてください。
Q. すでにスマホを持たせてしまいました。今からでも遅くないですか? A. 全く遅くありません。今日から話してください。「改めて大事な話がある」と切り出せば、お子さんも真剣に聞いてくれるはずです。