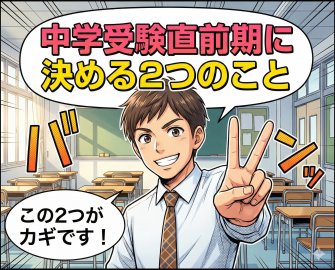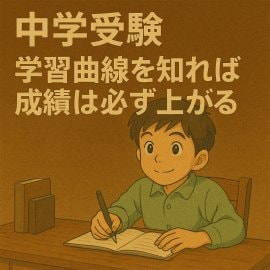2025.04.07
新学年スタートの注意点 - 子どものサポートするために注意点
いよいよ4月になり、新学年のスタートですね。
お子さんは新しい学年になって、気持ちが引き締まっていますか?
新学年は環境が大きく変わる時期。子どもに大きな変化が起こるため、親としては注意が必要です。
また「今まで出来なかったこと」にチャレンジできるチャンスの時期でもあります。がんばっていきましょう!
今回は新学期の注意事項をご紹介します。
1. 友達関係に注目しよう
新学期になると、クラス替えがありますね。このとき最も注意すべきは「友達関係」です。
新しいクラスになって、友達関係に変化はないか観察しましょう。
友達ができることは大切ですが、クラスメートによって子どもの1年間は大きく影響されます。
特に、お子さんが以下のような性格の場合は注意が必要です:
- 「少し騒がしい」
- 「落ち着きがない」
- 「周りに流されやすい」
周りに似たような子がいると、授業に集中できなくなることがあります。
また「いじめ」にも注意が必要です。今まで仲良しだった子とクラスが変わったために、いじめの標的になるケースもあります。
文部科学省のデータによると、小学生では「小2」、中学生では「中1」が最もいじめが多い学年です。中学1年生のお子さんをお持ちの方は特に注意してください。
<対策>
- 子どもの様子を注意深く観察する
- 学校の様子をよく聞く
- いつもより気を配る
<体験談>
石川県 匿名希望様からのメッセージ:
先生、いつもメッセージありがとうございます。
今回の内容にも全く同感しました。我が家は4年生の男の子です。
3年生のときにクラブ活動に参加させたところ、そこでいじめに遭い、なかなかその状況に気づいてやれませんでした。
その後、同じクラスの今まで仲が良かったお友達からも嫌がらせを受けるようになりました。
すると息子は、そのお友達に対して遊んで欲しさから、しつこくつきまとうような行動に出てしまいました。
なかなか息子の気持ちがわかってやれず、大変に悩んだ年でした。
4年生の時は、その仲良しだった友達とも別のクラスになり、クラブも半年でやめさせたので、新たな気持ちでスタートした1年だったのですが、とってもいい1年でした。
ようやく新たな友達も見つかり、5年生になってクラスが違っても遊ぶんだと言える友達のようです。
4月にまた新しい環境がスタートするので、いろいろな心配がありますが、息子が頑張れるように見守ってやりたいな~という気持ちになれました。
2. 学級崩壊のリスクに備える
小中学校では、クラスによって「学級崩壊」が起きる場合があります。特に注意が必要なのは:
「前の学年の先生がすごく良かった場合」
これは大切なポイントです。なぜなら、子どもは前の先生と比べてしまい、新しい先生の「悪いところばかりが目に付く」からです。
親も「○○先生のときは良かった」というようなことを口にしがちです。
私の指導している生徒の中には、小学校での「学級崩壊」が原因で、中学校になっても学習の遅れが尾を引いている子もいます。
ある小学校では「算数の授業が長くて30分、短くて10分」という状況もあります(残りの時間は先生が生徒を注意している状態)。
<対策>
「授業ができていない」ことがわかった時点で:
- 担任と相談する
- 家庭で子どもの学習対策を立てる
「学校が悪い」と言っても解決しません。子どもの学習については、家庭でしっかりフォローしていきましょう。
<体験談>
徳島県 匿名希望様からのメッセージ:
マンモス校ですが、10人ほどの生徒が授業妨害・怠学等、学年10クラスをかき回してくれます。
授業中も学校に来たら教室に入らず廊下や校庭、中庭等で大声を出したり暴れたり、駐輪場の自転車を壊したり…。子どもは授業に集中できません。
先生はその子たちに振り回されているようです。当然、授業も進みません。教室にいる子どもの中にも廊下から声をかけていくし、授業の中断、また授業以外の時間にも暴力をふるったり、安心して学校にいられないと言っています。
でも学校を休ませることもできず、「身体的危険を回避することを1番に」登校しています。授業中、教室内で喫煙している生徒を先生が注意しない(?!)という話も…。
女性の先生は一人では注意もできないような状態だそうです。先生も頑張ってくれているのでしょうが…。
冗談か本気か、「転校しようか」と子どもに言われたときはギクッとしました。
3. 受験生の環境を見極める
受験生の場合は、そのクラスが「合格しやすいクラス」か「不合格になりやすいクラス」かに注意しましょう。
「合格しやすいクラス」は:
- 静かで勉強しやすいクラス
- 騒がしくても一致団結できるクラス
「不合格になりやすいクラス」は:
- 騒がしく落ち着きがないクラス
- 物事に集中して取り組めないクラス
興味深いことに、不合格者は特定のクラスに集中する傾向があります。例えば「不合格者が6人」という場合:
イメージの分布:
1組 1人 2組 1人 3組 1人 4組 1人 5組 1人 6組 1人
実際の分布:
1組 1人 2組 0人 3組 4人 ←ここに集中 4組 1人 5組 0人 6組 0人
これは学校単位でも同様の傾向があります。地区での不合格者30人の例:
A中学 2人 B中学 3人 C中学 16人 ←ここに集中 D中学 4人 E中学 5人
これは学校が「荒れている」場合、先生の注意が問題行動に集中し、授業が成立しにくいことが原因です。実際に同一地区内のテストで、学年平均に100点の差があったケースもありました。
<対策>
受験生については、基本的に学校だけに頼らないほうが安全です。理由は:
- 統一テストがないため基準がない
- 進路指導の経験が蓄積されていない先生も多い
具体的には:
- 全国レベルの実力テストを受けて正確な実力を把握する
- テスト結果を見て、受験対策を立てる
問い合わせ・ご相談はこちらから