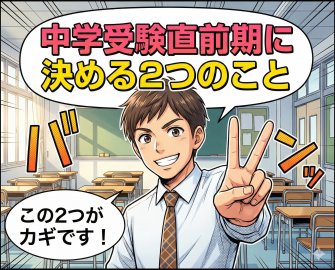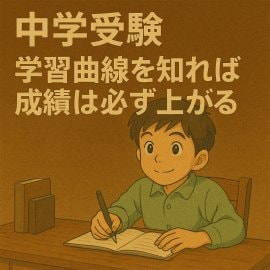2025.01.25
反抗期の怒りの正体
中学生を中心に指導してきた私の教室。小学生や高校生もいましたが、圧倒的に多かったのは「中学生」でした。成績、親の離婚、いじめ、友人関係...この多感な時期、生徒たちは様々な問題を抱えていました。
中でも親御さんが最も頭を悩ませるのが「反抗期」。今日はこの反抗期について、私自身の経験と指導者としての気づきをお話ししたいと思います。
■私の反抗期、その怒りの日々
私の反抗期は小5から中1。当時は「大人」に対して、説明のつかない怒りが渦巻いていました。
印象的だったのは「川での遊泳事件」。自宅前の川で泳いでいるところを先生に見つかり、反省文を書くことに。友達は素直に「もう川では泳ぎません」と書いたのに、私は違いました。
書いた内容は「大人が憎い」という過激なもの。ちょうどロッキード事件があった時期で、「大人は子どもに偉そうなことを言うくせに、自分たちは悪いことをしている」という怒りでいっぱいでした。
結果、1年間のプール使用禁止という厳罰が(笑)。
中1になっても反抗は続き、怖い女性の社会科教師と喧嘩して「点数のことばかりグチグチ言うなら、テストすればいいじゃないか!」なんて言い返したり。クラスメイトからは冷ややかな目で見られましたね。
朝ごはんに卵焼きがないだけでブチ切れて、食べずに学校に行ったこともありました。理由もわからない怒りが次々と湧いてきて、時には「人を刺してしまうのではないか」というくらいの感情の高ぶりを感じていました。
■反抗期の正体〜科学と経験から見えてきたもの
後に教師となり、生徒の反抗に直面する中で、あの頃の自分の気持ちが理解できるようになりました。調べていくうちに、科学的な説明も見つかったんです。
この全ては「成長ホルモン」の仕業。このホルモンの影響で、イライラ、落ち込み、気分の高揚が激しくなります。まるで「自然の薬物」のような状態なんです。
子どもたちの言葉を借りれば: 「親はうざい」「先生邪魔」「大人うっとしい」 ...でも、かまってもらえないと何だか寂しい。
■教室での実践〜反抗期の生徒との向き合い方
教室でワークを投げつけられることもあります。そんな時は容赦なく叱ります。普段は冗談を言い合える関係だからこそ、叱ったときの効果は絶大なんです。
私の対応の基本は「ほっておく」。でも、「ここは越えちゃダメ」という一線を越えそうな時だけは、思いっきり叱ります。
「親」という漢字のように、「木」の上に「立」って子どもを「見」る。遠くから見守りつつ、必要な時だけ近づく。これが私の基本姿勢です。
■反抗期の子を持つ親御さんへ
よく受ける相談が「子どもが反抗期で、すぐに怒ります。どうしたらいいでしょうか...」というもの。
私からの提案は2つ:
- 子どもと一緒に理解を深める
- これは成長ホルモンの影響だと説明する
- 風邪薬の副作用のように、感情の波も「成長の証」として受け入れる
- 基本は「見守る」だけ
- 過度に干渉しない
- 本当に必要な時だけ、しっかり叱る
- 気づいていても、あえて目をつぶることも大切
これって実は夫婦関係に似ています(笑)。「その食べ方は下品よ」「服のセンスをなおして」...なんて、一々言われたらうんざりしますよね。
全てを指摘する必要はないんです。時には片目をつぶって、本当に必要な時だけ注意する。それが長期的な関係を築くコツです。
反抗期は誰にでもある成長の過程。決して異常なことではありません。この時期を、理解と愛情を持って乗り越えていってください。いつか必ず、大切な思い出として振り返れる日が来るはずです。
毎日音声で話が聞けます。聞きたい方はこちら