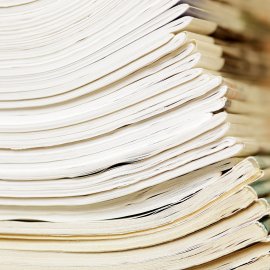2025.02.23
眼科学通信(5)眼科医療トピック
眼科では年間にしておよそ5500名の患者(紹介率60%)を診療しているが、過去十年間には目をみはる変遷と進歩があった。いくつかのトピックを挙げてみよう。
まず、治療面では、激増した重度の糖尿病網膜症に対処するために硝子体手術を活発に実施し、一定の成績を収めている。増殖硝子体網膜症(重度網膜剥離)は従来は失明を余儀なくされていたが、最近は硝子体手術によってかなりの患者を失明から救うことができるようになった。眼内の出血や増殖膜の除去、剥離網膜の復位、眼内光凝固、眼内ガスタンポナーデなどの手技が訓練されたエキスパートによって数時間かけて行われている。また、高齢化とともに老人性円板状黄斑変性や突発性黄斑円孔などが増加していることは間違いない。これらの疾病も従来は全く治療法がなかったのであるが、数年前に新たに開発された手術療法を我々も活発におこない良好な成績を収めている。世界の先端を切っていると目される米国ワシントン大学に留学している上村講師からの便りによれば、我々の教室における手術手技と成績はまったく遜色ない、とのことえ自信を深めているところである。
老人性白内障も増加しているが、眼内レンズ移植術がほぼ完成して普及しており、外部の施設にまかせているのが現状である。上記の硝子体手術をはじめ眼窩腫瘍、眼瞼腫瘍、鼻涙管閉塞など、専門的な手技・経費・管理を必要とする治療分野、および新たな手術適応開発を目指した臨床研究に重点をおいて大学病院としての役割を意識して仕事を進めている。
一方、診断検査面のトピックを二つ挙げておく。一つは、HTLV-1 associated uveitis (HAU)という「ぶどう膜炎」である。これは中尾久美子講師が発見して詳しく研究してきたもので、神経疾患HAMの部分徴候として発生することもあれば、単独に発生することもある。いうまでもなくレトロウイルスHTLV-1が関連するものである。患者は視力低下(霧視)あるいは飛蚊症をきたして来院するが、数週ほどの経過で緩解するのが特徴である。炎症の再燃が少なくないが、大きな視力障害を残すことは稀である。南九州地区における「ぶどう膜炎」の数パーセントを占めており、この新しく確認した疾病が国内外で追認されていることは教室の誇りである。
もう一つは、遺伝子診断である。レーベル視神経症、網膜色素変性を代表とするいくつかの遺伝性眼底疾患における分子病理学レベルでの一義的診断が可能になってきた。国内はもとより最近はアジアの国々からも遺伝子診断を依頼して試料が送られてくるようになった。このような遺伝病には治療法がまったくないのが遺憾であるが、治療法開発に向けての基礎的研究として、分子レベルでの疾病理解に努力している現状である。
以上、大学病院における眼科診療は、内科的および外科的研究の進歩に対応して診断・治療の両側面から大きな変貌を遂げようとしている。高齢化に対処するため臨床に直結した診療研究に多忙な毎日を過ごしている昨今である。
(出典:鹿児島県医師会報、平成9年8月)