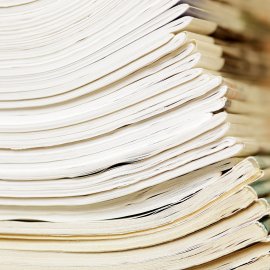2025.02.10
眼科学通信(4)眼科と他科との連携
眼科における日頃の診療教育活動について他科との連携という視点から書いてみよう。視覚器に病変を来す全身病は診療全科にまたがり、その数は数百とも言われる。他科との連携プレーには、当科から他科に診療をイライする、他科から視覚器に関する情報を求められる、という二つのカテゴリーがある。他科に依頼する事例はさまざまであるが、眼科には症候群が数多くあるから、診断検査を求めることが少なくない。また、治療の主力は手術であり、最近は手術適応件数と実施件数とが顕著に伸びている。約六割が局所麻酔、残りが全身麻酔で行うが、リスクをかかえる高齢患者においては、術前_術後の全身管理に留意することが従前にも増して大切になってきた。
当科における診療システムを参考までに述べると、主として医員(研修医)が外来・病棟の患者を一貫して受け持つ。各医師は外来専従あるいは病棟専従ではなくて外来・病棟を並行して行なっている。該当する医員(研修医)・医員は入局後少なくとも三年間、しばしば四年から五年にわたって当科で研修するから、患者からみると最短でも二年間、しばしば数年にわたって同じ主治医に診てもらうことになる。月・水・金は主として外来に、火・木は主として手術に専念する。外来・入院を通じて一貫して診ていくシステムは研修成果をあげるのに有効なだけでなく、患者サイドからもわかりやすく、医師〜患者関係をはぐくむのにも効果的である。文部教官が専門研究領域とのかねあいで主治医になることもあるが、すべての患者は、診断にせよ治療にせよ講師以上の上級医師がマンツーマンで指導している。
さて、院内各科との連携は紹介状や依頼状を書くことからはじまる。医療の実践においてはさまざまな文書を適切に作成することが要求されるが、診療録や紹介状の書き方に王道はない。しかも医学生時代に文書作成技法について教えられる場はほとんどないから、入局してから見よう見まねで習得させている。紹介や依頼に際しては、ジャーゴン(仲間うち言葉)は避けること、難解な専門語や欧文略語は用いないこと(珍しい疾病などを略称されても理解できない)、専門的な知識や技術の表現は避けること(視力の数値などを細かく書いても意味がないことが多い)紹介の目的が何であるかを簡潔明瞭に述べること、冗長な挨拶表現などは省略すること(院内紹介はお互い様である)、といったことに留意して指導している。また、他科からの紹介に対する回答についても同様に留意している。盛り込まれた情報が誰にも(看護師にも)わかりやすく伝わることが大切であろう。
ちなみに、当科の診療録はできるだけ日本語での記述を心がけている。国際標準語としての英語を重視しないのはまずいという見方があるとすれば、時代に逆行すると言わざるを得ない。臨床医学の底が浅かった昭和三十年代に私が受けた医学教育は、明治以来の習慣をひきずった独語・英語混じりの日本語によるものであった。診療録の全文を独語あるいは英語で記述するのを自慢する意思さえいた。日本人患者を対象とした診療・臨床研究・教育との整合性が乏しいと感じたものである。間も無く留学した米国では当然のごとく母国語のみで情報が伝達・記録されていた。昭和五十三年に鹿大に赴任してからは、診療録はもとより医師間のやりとりは日本語を用いるのをルールとした。当科には悪性腫瘍は稀であることも運用しやすいのかもしれない。このような診療録は看護師が読んでも(場合によっては患者や家族が読んでも)適切かつ容易に情報をつかみとることができる。また、診療録及び関連資料のすべては昭和五十年度分から医局に保存している。子供の時に手術した患者が十数年後に再来してくる事例は稀ではなく、その昔の診療データがすこぶる役立つことが多い。また、十年ほど前からパソコンを活用して、患者氏名・性・年齢・病名といったキーワードだけではあるが、八万件以上のデータから構成される「鹿児島大学眼科外来診療データベース」を作成することに成功している。過去二十年間の診断困難事例や治療困難事例の検索・抽出などをたちどころに行い、類似症例の実際経験を活用できるようになった。地域における唯一の大学病院として、貴重な学術資産というべき診療データを永く残し、次世代あるいは次々世代における南九州地方における眼の疾病構造の変遷や遺伝情報の活用に役立ててもらいたいものである。
(出典:鹿児島大学病院意思会報、平成九年十月)