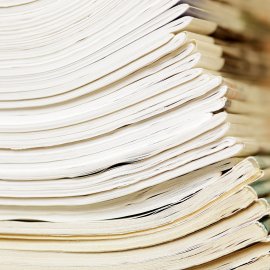2025.02.10
眼科学通信(3)私の研究と松本清張の推理小説
死者の網膜に最後に残った映像が検出できれば、殺人犯罪捜査の上ではかりしれない利益をもたらすにちがいない。最後の場面に登場している人物こそ犯人または犯行にかかわりのある重要人物でなければならない。その網膜にインプットされた映像を検出し、記録することがよなら、直ちに犯人を正確に指摘することができるであろう。推理小説や探偵小説の作家たちは、こうした状況に大いなる関心を示してきたようである。例えば、江戸川乱歩の随筆集『幻影城』にはこういう部分がある5「死の刹那に見た犯人の顔が、解剖すると網膜に残っていて、犯人推定の手掛かりになる。こういう話は昔からあって、よく小説にも使われたが、科学的には否定されていた…」
キューネは古く19世紀末、網膜視細胞の感光色素ロドプシンを先駆的に研究したドイツの化学者であるが、カエルの眼底に明暗の映像を作り、ロドプシンの分解の程度に応じて刻印されたオプトグラムを観察している。私は1969年から2年間、米国ミシガン大学でレチナルデンシトメーターという重厚な実験装置を用いて、ヒトのロドプシンと錐体色素の研究に従事したことがある。私の専門は眼科で網膜のさまざまな病気の原因にどう関わるのかに興味があったから、帰国してからオプトグラムの原理を応用して改良した眼底カメラを用いて感光色素を調べてみた。被検者を暗いところにとどめておいてロドプシンを増加させておき、強い格子縞の光を見せる。そうすると網膜には格子縞が映る。明るい部分の網膜ではロドプシンが分解して減少し、暗いところのロドプシンの量は変わらない。均等なフラッシュを与えて眼底写真をとると、ロドプシンが少ない部分は多くの光を反射して明るく写り、ロドプシンが多く残っている部分ではより多くの光が網膜で吸収されるから暗く写る、全体として格子縞の写真になる、というのが原理である。被検者の絶大な協力が必要なので、多くの患者に応用するわけにはいかなかったが、ロドプシンのみならず網膜の中心部に密集して色覚に直接関係する錐体色素のオプトグラムの写真撮影にも成功した。
さて、松本清張氏から1989年、私の研究を引用して長く構想を温めてきた犯罪小説を書きたいという書信をもらった。氏は当時、慢性の眼病を患ってもおられたので、学術論文をお送りしたがよく理解できなかったようで、文藝春秋社の担当者を鹿児島まで数回にわたって派遣されて私の研究を間接的ながら取材されたのであった。ほどなく「文藝春秋」(1990年5月号)および作品集「草の径(文藝春秋、1991年)」に収められた『死者の網膜犯人像』を手にすることができた。私のことは、この作品で次のように紹介されている。「眼科医学が発達して死者の網膜映像を再現する高度技術が開発されて、法医学に寄与するとなれば、どんなに画期的かわからない。これは大方の願望である… 願望を実現できそうな、そういう研究はなされているのだろうか。その医学的技術開発にとりくんでいる学徒に、R医科大学眼科教室のZ教授がある…」名にしおう大作家に、若い時に熱中した研究が紹介されたことは光栄この上もなく、専門の医学雑誌に引用される以上に大きな喜びを感じたものである。
(Color&Colorist. 創刊準備号、平成12年)